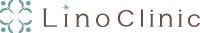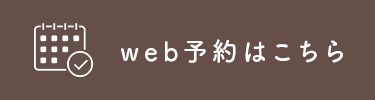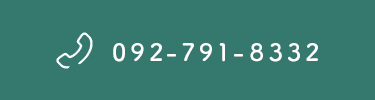「夜中に何度も目が覚めてしまう…」「一度目が覚めるとそこから眠れない…」といったお悩みはありませんか?これらは「中途覚醒」と呼ばれる睡眠障害の一つで、睡眠の質を大きく低下させる原因になります。
中途覚醒は、加齢やストレス、生活習慣の乱れ、身体的・精神的な疾患など、さまざまな要因で起こります。放置すると、日中の集中力低下や疲労感、気分の落ち込みなど、心身の不調を引き起こしやすくなるため注意が必要です。
このコラムでは、中途覚醒の主な原因をわかりやすく解説し、ぐっすり眠るための具体的な対策を10選紹介します。夜中に何度も目が覚めてしまう方や、質の良い眠りを取り戻したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
中途覚醒とは、夜中に何度も目が覚めてしまう睡眠障害の一つです。寝つくことはできても、睡眠の途中で目が覚め、その後なかなか再入眠できない状態が続くのが特徴です。特に高齢者に多く見られますが、若い方でもストレスや生活習慣の乱れなどが原因で起こることがあります。
中途覚醒は、睡眠の深さやリズムを乱し、質の良い睡眠を妨げます。その結果、朝起きたときに「寝たはずなのに疲れが取れない」「体が重い」と感じることが多く、日中の集中力低下やイライラ、意欲の低下にもつながります。
原因としては、ストレスや不安、うつ病などの精神的な要因のほか、睡眠時無呼吸症候群、頻尿、慢性的な痛みなど身体的な問題も関係します。また、寝室の環境(温度、湿度、音、光)や寝る前の生活習慣も影響します。
中途覚醒を改善するためには、原因を見極めた上で生活習慣の見直しやリラックス法を取り入れることが大切です。症状が続く場合は、専門医に相談することをおすすめします。
睡眠障害による中途覚醒の主な10個の原因

ストレスや不安
仕事の締め切りや人間関係のトラブル、将来の不安など、日常のストレスは脳を常に「戦闘モード」にし、夜間も心が休まらず中途覚醒を引き起こします。「夜中に目が覚めたらどうしよう」という不安自体もさらなる覚醒を誘発します。例えば、上司とのトラブルを考え続けた夜や、大事な会議の前日は特に眠りが浅くなります。
こうした場合、寝る前にスマホを手放し、深呼吸や軽いストレッチ、ハーブティーを飲むなどリラックス習慣を作ることが効果的です。
アルコール摂取
「お酒を飲むと寝つきが良い」と思いがちですが、実はアルコールは眠りの後半に脳を覚醒させる作用があります。特に深い睡眠を妨げるため、夜中に何度も目が覚めやすくなります。さらに利尿作用があるため、トイレに起きる回数も増加します。たとえば晩酌を習慣にしている人は、朝に強いだるさや疲労感を感じることが多いです。
快眠のためには寝酒を控え、飲む場合も就寝3時間前までにするのが望ましいです。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」は、中途覚醒の代表的な原因です。呼吸が止まるたびに脳が「息をしなさい」と覚醒命令を出すため、眠りが何度も中断されます。いびきが大きい、朝起きても疲れが残る、日中強い眠気があるなどの症状が特徴です。
例えば、夜間に何度も目が覚めてしまう方は、この病気が隠れている可能性があります。放置すると高血圧や心疾患のリスクがあるため、早めに専門医の診察を受けることが重要です。
うつ病などの精神疾患
うつ病や不安障害などの精神疾患では、夜中に目が覚める中途覚醒がよく見られます。特にうつ病では「早朝覚醒」と呼ばれる、予定よりかなり早く目が覚めてしまう症状が特徴的です。例えば、深夜3時に目が覚め、その後眠れずに悩む人が多いです。
気分の落ち込み、食欲低下、興味喪失などの症状が伴う場合は、精神科や心療内科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。早期治療により睡眠改善とともに心の回復も期待できます。
夜間に何度もトイレに行く
「夜間頻尿」は、夜間に尿意で目が覚める状態です。加齢による膀胱機能の低下、前立腺肥大、塩分過多の食事、就寝前の多量の水分摂取が原因となります。たとえば、寝る前に水やお茶を多く飲む習慣があると、夜間に何度もトイレに起き、眠りが分断されます。転倒リスクが高まる高齢者では特に注意が必要です。
塩分や水分摂取量を見直し、症状が続く場合は泌尿器科の診察を受けることが推奨されます。
むずむず脚症候群
「脚がむずむずしてじっとしていられない」という感覚が特徴のむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は、入眠障害だけでなく中途覚醒の原因になります。夜間や就寝時に強く症状が出るため、何度も目が覚めてしまい、しっかり休めません。
例えば、寝ている間に無意識に脚を動かして目が覚める人も多いです。鉄不足や遺伝が関わることがあり、症状が続く場合は内科や神経内科での診断と治療が必要です。
加齢による影響
年齢とともに深い眠り(ノンレム睡眠)の割合が減り、眠りが浅くなるため、少しの音や不快感でも目が覚めやすくなります。また、加齢に伴うホルモン分泌の変化により体内時計が前倒しになり、夜中や早朝に目が覚めてしまう「早朝覚醒」が増えます。例えば、夜中に物音で目が覚め、再入眠できず朝まで起きてしまうケースもあります。
寝室環境を整える、昼寝を控えるなど、生活の工夫で改善が期待できます。
生活リズムが一定ではない
仕事のシフト勤務や夜勤、不規則な就寝・起床時間などで生活リズムが乱れると、体内時計がずれ、睡眠が浅くなり中途覚醒が起きやすくなります。例えば、休日に昼まで寝る、平日は寝不足で週末に寝だめするなどの生活は特に悪影響です。
毎日同じ時間に寝起きする、朝に太陽の光を浴びるなど、体内時計を整える習慣をつけることが改善への近道です。
頭痛で目が覚める
偏頭痛や緊張型頭痛など、夜間に起きる頭痛は睡眠を中断させる原因になります。特に寝返りや枕の高さが合わない場合、夜中に痛みを感じて覚醒してしまうことがあります。例えば、合わない枕で首が圧迫され、目が覚めるケースはよくあります。
枕やマットレスの見直し、寝る前のリラックス習慣、頭痛の治療が重要です。慢性的な頭痛がある場合は、専門医での診察をおすすめします。
悪夢を見て目が覚める
悪夢は、強い恐怖や不安を伴う夢で、睡眠中に脳を強く興奮させ中途覚醒を引き起こします。例えば、追いかけられる夢や落ちる夢で目が覚め、その後眠れなくなる人もいます。悪夢はストレス、トラウマ、薬の副作用、精神的な不調などが原因で起こることがあります。
頻繁に悪夢が続く場合は、ストレスケアや専門医の診察が必要です。寝る前に心を落ち着ける時間を作ることも有効な対策になります。
中途覚醒について相談してみる
中途覚醒を改善するための対策10選

中途覚醒が続くときの、症状を改善するための方法を10つご紹介します。
睡眠リズムを一定にする
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることで体内時計(サーカディアンリズム)が安定します。平日・休日関わらず起床時間をずらさず、遅くまで寝だめするのは避けましょう。
例えば、毎朝7時に起きると決めたら、休日も同じ時間に起き、夜も自然と決まった時間に眠気が来るようになります。朝起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びるとより効果的です。
呼吸法や瞑想でリラックスする
寝る前に「4-7-8呼吸法」を試してみましょう。4秒かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけてゆっくり口から吐きます。これを3〜5回繰り返すだけでもリラックス効果があります。
瞑想は呼吸に意識を向け、頭の中の考えを手放すことがポイント。ベッドに入る前に部屋の照明を暗めにして、静かな音楽を流すとより深いリラックス状態を作れます。
寝室の環境を整える
静かで暗く、適温(18〜22℃目安)に保った寝室は快適な睡眠の基本です。枕やマットレスは自分の体に合うものを選びましょう。例えば、硬すぎる枕は首の負担になり、中途覚醒の原因になります。
光が入る場合は遮光カーテンを、騒音が気になる場合は耳栓を使用しましょう。加湿器や除湿機で湿度(50〜60%目安)を調整するとより快適です。
就寝前に飲食しない
寝る2〜3時間前までに食事を終えることが理想です。寝る直前の重い食事は胃腸を刺激し、夜中の覚醒を招きます。特にカフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、チョコレート)は夕方以降は控えると良いです。水分も寝る1時間前からは少なめにし、夜間のトイレ覚醒を防ぎましょう。
どうしてもお腹が空いた場合は、消化に優しい温かいスープなどを少量摂るのがおすすめです。
寝る前のスマホやパソコンの使用を控える
スマホやパソコンの画面から出るブルーライトは脳を覚醒させる原因になります。寝る1時間前からは電子機器をオフにし、紙の本を読んだり、日記をつけたりして過ごしましょう。
どうしてもスマホを使う場合は、ブルーライトカットモードを設定し、画面の明るさを最小限にしてください。寝室にスマホを持ち込まない習慣をつけるとより効果的です。
日中は適度に運動する
日中に軽い運動を取り入れると、夜に自然な眠気が訪れます。ウォーキング(1日30分程度)、ストレッチ、軽い筋トレ、ヨガなどが最適です。
ただし、激しい運動は交感神経を活性化させるため、寝る3時間前までに終わらせましょう。例えば、夕方に軽く散歩をするだけでも、体温調節のリズムが整い睡眠の質が上がります。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かる
就寝1〜2時間前に38〜40℃のお湯に15〜20分ほど浸かると、体温が一時的に上がり、入浴後に体温が下がるタイミングで自然に眠気が訪れます。入浴中にラベンダーやカモミールのアロマオイルを使うとリラックス効果が高まります。
入浴後はすぐに冷たい部屋に移動せず、体が自然に温度を下げるのを待つとよりスムーズに眠りに入れます。
飲酒喫煙を控える
アルコールは寝つきを良くするように思われがちですが、深い眠りを減らし夜中の目覚めを増やします。喫煙に含まれるニコチンは覚醒作用があり、寝つきを妨げます。寝る前だけでなく、日常的に減らすことで睡眠の質が向上します。
どうしてもお酒を飲む場合は就寝3時間前までにし、量も控えめにしましょう。
眠くなってから布団に入る
「早く布団に入って眠ろう」と考えるのは逆効果です。眠くなる前に布団に入ると、かえって「眠れない」という不安が強まり、脳が覚醒してしまいます。
眠気を感じたタイミングで布団に入り、もし20分以上眠れなければ、一度起きてリビングで静かに過ごし、再び眠気が来るのを待つのが効果的です。
中途覚醒が続く場合は病院へ相談する
生活改善を試しても改善しない場合は、睡眠時無呼吸症候群や精神疾患、他の身体的病気が関係している可能性があります。
心療内科や睡眠専門外来など専門医の診察を受け、原因を特定し適切な治療を受けることが重要です。早期に専門家に相談することで、根本的な改善を目指せます。
中途覚醒について相談してみる
中途覚醒の治療法

中途覚醒は生活習慣の改善だけでは改善が難しい場合があります。そんなときには、医学的な治療を検討することが大切です。ここでは主な治療法として「薬物療法」「認知行動療法(CBT)」「TMS治療(磁気刺激療法)」について詳しく解説します。
薬物療法
薬物療法は、症状が重い場合や生活改善だけでは十分な改善が見られない場合に用いられます。睡眠薬や抗不安薬などが処方され、薬の種類や作用時間によって使い分けられます。
超短時間作用型
超短時間作用型の睡眠薬は、寝つきは良いが夜中に目が覚める「中途覚醒」を特に改善したい場合に使用されます。血中濃度が短時間で下がるため、翌朝の眠気やふらつきなどの「持ち越し効果」が少ないのが特徴です。ただし、効果が早く切れるため、再び目が覚めてしまう場合もあります。
服用のタイミングや量に注意が必要で、医師の指導のもと正しく使うことが重要です。
短時間作用型
短時間作用型の睡眠薬は、寝つきの悪さと中途覚醒の両方に対応できる薬です。比較的持続時間がありつつ、翌朝の影響が少ないため、バランスがとれた選択肢です。中途覚醒後の再入眠を助ける効果も期待できます。
ただし、依存や耐性のリスクがあるため、長期使用は避け、医師の管理下で使用することが大切です。
中間作用型
中間作用型の睡眠薬は、夜中に何度も目が覚める人や、早朝に目が覚めてしまう人に適しています。作用時間が比較的長いため、夜間の覚醒を防ぎ、より深い睡眠を促します。
一方で、翌朝の眠気やだるさが出る可能性があるため、翌日の予定や体質に応じて処方されます。
長時間作用型
長時間作用型の睡眠薬は、睡眠の維持が特に難しい人や、夜間に長く目が覚めてしまう人に使用されます。効果が長く続く分、翌朝の持ち越し効果が出やすい点には注意が必要です。
日中に強い眠気が出ることがあるため、高齢者や日中の活動が多い人には慎重な判断が必要です。
認知行動療法(CBT)
認知行動療法は、睡眠薬に頼らず根本的に睡眠障害を改善する方法として注目されています。中途覚醒では、夜中に目が覚めることへの不安や「また眠れなくなるのでは」という恐怖感が、さらなる覚醒を引き起こします。
CBTではこうした誤った思考を修正し、睡眠への過剰な不安を減らします。
具体的には以下のような方法が含まれます。
-
睡眠制限法:寝床にいる時間を制限し、睡眠の質を高める
-
刺激制御法:寝室を「眠る場所」として条件づける
-
リラクゼーション法:深呼吸や筋弛緩法で心身を落ち着ける
-
認知再構築:「眠れないと大変だ」という極端な考えを現実的に修正する
CBTは再発予防にも効果的で、副作用がない点が大きな魅力です。医師や専門カウンセラーの指導のもと、数週間〜数ヶ月かけて進めるのが一般的です。
TMS治療(磁気刺激療法)
TMS(経頭蓋磁気刺激療法)は、脳に磁気を当てて神経活動を調整する新しい治療法です。中途覚醒の背景にあるうつ病や不安障害など、精神的な問題が関わる場合に効果が期待できます。
TMS治療では、磁気を用いて脳の特定の部位を刺激し、神経ネットワークの働きを正常化します。これにより、不安感の軽減、気分の安定、睡眠の改善が見込めます。薬のような依存や副作用が少なく、治療中も日常生活が送れることが大きなメリットです。
TMS治療は日本でも徐々に普及しており、治療期間は通常4〜6週間程度、週に数回の通院が必要です。効果には個人差がありますが、他の治療で効果が得られなかった方にとって新たな選択肢となり得ます。(当院では行っておりません。)
まとめ
中途覚醒は「夜中に何度も目が覚めてしまう」という辛い症状で、睡眠の質を大きく低下させ、日中の集中力低下や疲労感、気分の落ち込みなど、さまざまな不調につながります。原因はストレスや不安、アルコール摂取、睡眠時無呼吸症候群、精神疾患、加齢、生活習慣の乱れなど多岐にわたります。
改善のためには、まずは生活習慣の見直しが重要です。睡眠リズムを整える、寝室の環境を改善する、呼吸法や瞑想でリラックスするなど、毎日の小さな積み重ねが質の良い睡眠を取り戻す第一歩になります。それでも改善が見られない場合には、薬物療法や認知行動療法など専門的なアプローチを検討することが大切です。
「夜中に目が覚めるのは年齢のせいだから仕方ない」と諦めず、適切な方法でしっかりと対策をとることが心身の健康を守る鍵です。睡眠に悩む方は、一度ご自身の生活を見直し、必要であれば専門医に相談してみてください。ぐっすりと眠れる夜を取り戻し、毎日をより健やかに過ごせるようにしましょう。
中途覚醒で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。中途覚醒は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」 「しっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院のご案内
中途覚醒や不眠症は、心と体に大きな負担をかけるため、早めの対策が大切です。メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、睡眠障害に関する専門的な診療を行っており、一人ひとりの症状や悩みに合わせた治療をご提案しています。
当院は 土日祝日も20時まで診療 しており、赤坂駅や天神駅から徒歩圏内 でアクセスも便利です。忙しい方でも通いやすく、当日予約も可能 です。
「夜中に目が覚めて眠れない」「日中に集中できない」などの症状にお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。あなたに合った方法で、安心して眠れる毎日を一緒に目指していきましょう。
中途覚醒について相談してみる