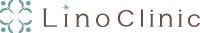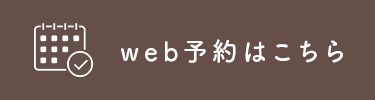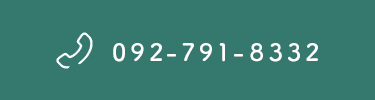更年期障害とは?

40代後半から50代にかけて、多くの女性が経験する「更年期」。この時期に現れる心身の不調は「更年期障害」と呼ばれ、体調や気分が優れないことに悩む方は少なくありません。これには、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少が関係しており、体のほてりや発汗、不眠、イライラ、気分の落ち込みなど、さまざまな症状が現れます。
本記事では、更年期障害の基本的な仕組みや原因、主な症状、受診の目安や対処法まで、分かりやすく解説します。
更年期障害とは?
更年期障害とは、主に40代後半から50代前半にかけて、多くの女性の身体的・精神的に起こる不調の総称です。
女性は年齢とともに卵巣の機能が低下し、最終的には月経が永久に止まる「閉経」を迎えます。日本人女性の閉経の平均年齢は50歳前後といわれており、その前後5年間(合わせて約10年間)を「更年期」と呼びます。この時期には加齢に伴う体の変化に加え、家庭や職場など社会的な要因や心理的要因が重なり、さまざまな不調を引き起こすと考えられているのです。
早い人は40代に入ってすぐ変化を自覚することもあり、症状が現れる時期や程度には個人差があります。
更年期障害とホルモンバランスの関係
更年期障害は、加齢に伴う女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量の減少が関係しています。
エストロゲンは、乳房の発達や皮下脂肪の増加など、女性らしい体つきを形作る働きがあり、子宮に作用して妊娠の準備を整える作用があるホルモンです。また肌のハリ・ツヤや骨量の保持に役立つ他、血管の健康を保ち、コレステロール値などを整え、脳の血流を増やし活性化するといった働きもします。
女性ホルモンは脳と連携しており、増やしたり減らしたりの調整はコントロールされています。加齢によってエストロゲンが低下しても、脳はホルモンを出すよう刺激を出し続けるため、結果的に自律神経のバランスが乱れ、身体的・精神的なさまざまな症状が現れると考えられているのです。
年齢に比例して変化する更年期症状の種類
更年期は、卵巣の機能が徐々に低下し、女性ホルモンの一つであるエストロゲンの分泌が大きく変動・減少していく時期です。このエストロゲンの急激な減少に伴って、心と体にさまざまな不調が現れます。
そして40代後半から50代前半にかけて、エストロゲンの分泌量はさらに不安定になり、増えたり減ったりを繰り返しながら、閉経を経て急激に減少していきます。このようなホルモンの揺らぎが自律神経の働きに影響し、のぼせや発汗、めまいといった自律神経失調症状につながるのです。
さらに、ホルモンの乱れによって、イライラや不安、不眠、抑うつなど精神神経症状が加わることも多く、日常生活に大きな影響を及ぼす場合もあります。頭痛、関節痛、肩こり、動悸、息切れなど、多彩な身体症状が重なる人も少なくありません。
閉経を迎えると、エストロゲンの分泌はほとんどなくなり、欠乏した状態が続きます。これにより、性交痛、頻尿、尿失禁、膀胱炎など非尿生殖器の症状が起こりやすくなる他、エストロゲンの持つ骨や血管を守る働きが失われることで、骨粗しょう症や動脈硬化、高血圧などのリスクも高まるとされています。
30歳代から更年期障害の症状が出 るケース
最近では、30歳代から更年期障害の症状が現れるケースも見られるようになりました。このような状態は「若年性更年期障害」と呼ばれ、通常の更年期障害とは異なり、閉経に伴う卵巣機能の低下とは関係しないことが多いとされています。
主な原因は、過度なストレスや極端な体重減少などにより、一時的にエストロゲンの分泌が低下することだと考えられています。頻度は高くありませんが、40歳未満で閉経してしまう「早発閉経」が原因の場合もあり、何らかの疾患や化学治療などの影響の可能性もあるため、医療機関への受診が必要です。
更年期障害の主な症状
更年期障害の症状は多岐にわたり、個人差が大きいですが、以下のような症状が一般的に見られます。
身体的な症状
- ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり):突然顔や上半身が熱くなる。
- 発汗異常:異常に汗をかく、または逆に汗をかきにくくなる。
- 動悸・息切れ:心臓がドキドキしやすくなり、軽い運動でも息切れを感じる。
- めまい・耳鳴り:急に目の前が暗くなる、耳鳴りがする。
- 不眠:寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める。
- 関節痛・筋肉痛:特に朝起きたときに関節がこわばる。
- 肌や髪のトラブル:肌の乾燥やしわが増え、髪のツヤが失われる。
精神的な症状
- イライラしやすい:些細なことで怒りっぽくなる。
- 気分の落ち込み:抑うつ状態になりやすく、何事にも興味がなくなる。
- 不安感:漠然とした不安を感じる。
- 集中力・記憶力の低下:物忘れが増え、集中力が続かない。
更年期障害の原因

更年期障害は、主に女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が急激に減ることで、心や体にさまざまな変化が起こる状態です。しかし、症状の出方やつらさには個人差があり、ホルモン以外にも多くの要因が関係しています。ここでは、更年期障害を引き起こす主な原因について詳しくご紹介します。
エストロゲンの急激な減少
更年期に入ると、卵巣の働きが徐々に低下し、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減ります。エストロゲンは以下のような役割を担っています。
- 自律神経のバランスを整える
- 気分の安定に関わる
- 骨密度や血管の健康を守る
- 肌や髪のうるおいを保つ
このホルモンが減ると、のぼせ・発汗(ホットフラッシュ)・動悸・イライラ・不安感・不眠など、さまざまな心身の不調が現れやすくなります。
ストレスの影響
40代〜50代は、家庭や仕事、親の介護などさまざまなストレスが重なる時期でもあります。加えてホルモンの変化が重なることで、心と体がストレスにとても敏感になるのが更年期の特徴です。
ストレスは自律神経のバランスを乱し、次のような症状を引き起こしやすくします。
- ホットフラッシュが強くなる
- 不眠が続く
- 気持ちが落ち込みやすくなる
- 疲れが抜けにくくなる
少しでもストレスを減らすために、趣味や好きなことに時間を使う・一人の時間をつくる・誰かに話すなど、気持ちを緩める工夫が大切です。
生活習慣の乱れ
不規則な生活や偏った食事、運動不足は、ホルモンや自律神経のバランスをさらに崩してしまう要因となります。
- 食生活の偏り → 栄養不足がホルモン合成や神経機能に影響
- 運動不足 → 血流が悪くなり、代謝や冷えに関係
- 睡眠不足 → 心と体の回復が妨げられ、疲労感が蓄積
更年期の症状を和らげるには、栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠がとても重要です。体にやさしいリズムを取り戻すことで、症状が軽くなることもあります。
遺伝的な傾向
家族の中に、更年期障害がつらかった方がいる場合、同じように症状が出やすい傾向があるとされています。特に、母親や姉妹に強い症状があった場合、自分自身も早めに準備をしておくことが役立ちます。
更年期障害は、単にホルモンの問題だけでなく、心や生活のバランス全体が関係している繊細な状態です。
不調を「気のせい」と我慢せず、自分をいたわり、必要なときは専門家の力を借りることも大切です。
更年期障害の受診の目安とは?

更年期の心身の変化は、「年齢のせいだから仕方ない」「いつか楽になるはず」と思って我慢してしまいがちです。しかし、無理を続けることで不調が長引いたり、生活に支障が出たりすることも少なくありません。
以下のような状態に心当たりがある場合は、一度医療機関を受診してみることをおすすめします。
日常生活に支障が出ているとき
- 疲れやすく、仕事や家事に集中できない
- 気分が落ち込み、何もやる気が出ない
- 不眠が続き、体力・気力が落ちてきた
- 外出や人と会うことがつらく感じるようになった
日常がいつものように過ごせないと感じたら、受診のサインです。放っておくと、心の不調が長引いてしまうこともあります。
心や体の症状が長く続いているとき
- のぼせ、発汗、動悸が治まらない
- 生理不順と一緒に強いイライラや不安感がある
- 腰痛や肩こり、頭痛など、体の不調が続く
こうした症状が「なんとなく不調」の範囲を超えて日常を脅かすレベルになっている場合は、早めの受診が安心につながります。
周囲から「大丈夫?」と心配されるようになったとき
自分では「まだ大丈夫」と思っていても、家族や同僚から心配されるようになったときは、一つの目安と考えてみましょう。心と体の不調は、自分で気づきにくいこともあります。
我慢しすぎていると感じるとき
「いつもの自分じゃない気がする」「頑張っているのにうまくいかない」
そんなふうに感じることが増えているなら、それだけ心や体が疲れている証拠かもしれません。
更年期障害は、医師のサポートを受けることで症状が軽くなることも多く、適切なケアを受けることで毎日の過ごしやすさが大きく変わります。
我慢せず、安心できる場所でご相談を
更年期のつらさは、人には伝わりにくく、自分でも「気のせいかも」と思いがちです。しかし、つらい症状があるなら、医療機関を受診してみてください。
まずは話を聞いてもらい、症状の改善に向けて適切なアプローチを実践していきましょう。
更年期障害の診断 について

更年期に入ると、体や心にさまざまな変化が起こります。しかし、「疲れやすい」「動悸がする」「気分が落ち込む」といった不調が、更年期障害によるものなのか、それとも別の病気が原因なのかを自分で判断するのは難しいことです。特に、更年期症状と似た病気(甲状腺疾患、うつ病、貧血など)もあるため注意が必要です。
更年期障害の診断では、主に患者さんの症状や生活の様子を基に総合的な判断が行われます。他の疾患との区別をつけるため、必要に応じて検査も併せて実施されます。
問診
問診では、以下のような項目について医師が詳しく確認します。
- 現在困っている症状の内容
- 月経の有無(周期や量、最終月経の時期など)
- 閉経からの期間
- 過去にかかった病気(特に子宮、卵巣、乳房に関するもの)
- 現在受診している病気や服用している薬の有無
- 家族歴(家族がかかったことのある病気)
- 生活習慣(喫煙・飲酒などの嗜好、運動習慣など)
- 日常のストレスの有無
こうした情報を基に、更年期障害であるかどうかを慎重に見極めていきます。
検査
問診の結果や症状の内容に応じて、検査が行われることもあります。主な検査項目は以下の通りです。なお、検査内容は医療機関の設備や方針によって異なる場合があります。
- 血圧、身長、体重の測定
基本的な全身状態を把握するために必要な測定です。
- 血液検査
女性ホルモン(エストロゲン、FSHなど)の分泌量、コレステロールや血糖値、肝機能、甲状腺機能などを調べます。
- 子宮・卵巣の検査
超音波検査、細胞診などなどを行い、他の婦人科疾患を除外します。子宮頸部細胞診は、1年以内に検査していない場合に行われます。
- 乳房の検査
触診やマンモグラフィー、超音波診断法などを通じて乳がんなどの異常がないか確認します。
- その他の検査
骨量測定(骨粗しょう症の確認)、心電図(心疾患の除外)、腹囲測定、血液凝固検査、心理テストなどを必要に応じて実施します。
更年期障害の診断は、これらの検査によって、似た症状を呈する他の病気(甲状腺疾患、うつ病、貧血など)の可能性を除外すること(除外診断)が非常に重要です。
更年期障害の治療法

更年期障害の治療は、「これをすれば必ず治る」というものではなく、症状や体質、生活背景に合わせて複数の方法が用いられることが多いです。
なお、治療法によっては医療機関ごとに対応が異なる場合もあります。
ホルモン補充療法(HRT)
ホルモン補充療法(HRT)は、更年期に急激に減少する女性ホルモン(エストロゲン)を外から補う治療法です。特に、ホットフラッシュ(のぼせ・発汗)、不眠、動悸、イライラなどの自律神経症状に対して効果が期待されており、骨粗しょう症の予防・改善にも有効とされています。
他にも、脂質異常の改善、肌の乾燥予防、不眠の軽減といった面でもサポートが期待できます。ただし、わずかですが乳がんや血栓症のリスクがあるとされているため、HRTを始める際は必ず医師と相談し、定期的な検診を受けながら慎重に進めることが大切です。
漢方薬
漢方薬は、体質や気質に合わせて処方できるやさしいアプローチとして、多くの方に選ばれています。
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):イライラ、不安、のぼせ、冷え、抑うつなど幅広い症状に対応
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):血流を良くし、肩こりや頭重感、月経不順の改善に効果が期待されます
漢方薬は、症状を総合的に整える力がある一方で、体質との相性が非常に重要です。自己判断ではなく、専門医のアドバイスのもとで取り入れることをおすすめします。
向精 神薬
更年期障害では、気分の落ち込みや不安感、不眠などの精神症状が強い場合に、抗うつ薬や抗不安薬などの向精神薬が用いられることがあります。これらの薬は気分の安定が期待できるため、日常生活の質を改善することにつながるでしょう。また、薬の種類によっては、ほてりや発汗など血管の拡張と放熱に関係する症状にも効果が見込めます。
プラセン タ療法
プラセンタ療法は、ヒト胎盤から抽出された成分を使用した方法です。プラセンタに含まれる成分は、ホルモンバランス調整作用や自律神経調整作用があるとされているため、更年期障害の、のぼせや発汗、イライラ、不安、不眠などの症状を改善する効果が期待できます。また、疲労感の軽減や肌のハリ・ツヤのサポートにも有効とされています。注射や内服で行われることが多く、保険適用となる場合もあります。
生活習慣の見直し
日々の習慣を整えることは、更年期障害の予防・改善の土台になるため重要です。
- バランスの取れた食事:特に、大豆イソフラボン(豆腐、納豆、豆乳など)はエストロゲンと似た働きがあり、女性の体にやさしく働きかけます。
- 適度な運動:ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、無理なく続けられる運動が自律神経を整え、気分の安定にもつながります。
- 質の良い睡眠:就寝前のスマートフォン使用を控え、ぬるめのお風呂やハーブティーなどでリラックスタイムをつくると、眠りの質が向上します。
心のケア(心理的アプローチ)
更年期は、「これまで通りにいかない自分」を受け入れなければならない時期でもあります。心の変化が大きく、自分でも戸惑いやすいタイミングです。
そのようなときは、カウンセリングやストレスマネジメントを取り入れることで、不安や孤独感、焦燥感を和らげられます。気持ちを言葉にして整理することで、本当につらかったことに気付くきっかけになるでしょう。
更年期障害は、誰にでも起こる自然な変化の一つです。けれど、「つらさ」や「戸惑い」の感じ方は人それぞれ。一人で抱え込まず、心と体の声に耳を傾け、必要なサポートを受けながら、自分らしく過ごせる方法を見つけていきましょう。
日常生活でできる更年期障害の対処法

更年期障害の症状は、人によって違いが大きく、体の不調だけでなく、心の揺らぎも伴うことがあります。
だからこそ、日々の生活の中で「自分にやさしくする時間」を少しずつ取り入れることが、とても大切です。ここでは、更年期症状を和らげるためにできるセルフケアの工夫をご紹介します。
食事を見直して、ホルモンバランスをサポート
食べ物は、私たちの体と心に直結しています。更年期には、エストロゲンの減少をやさしくサポートする栄養素を意識して摂りましょう。
● 大豆イソフラボン:女性ホルモンに似た働きをする。大豆製品(納豆、豆腐、豆乳)に多く含まれる
● カルシウム・マグネシウム:骨や神経の安定に必要なミネラル。小魚、海藻、アーモンド、バナナなどがおすすめ
● ビタミンB群・ビタミンE:疲れやすさやイライラの軽減に役立つ。豚肉、玄米、ナッツ類、アボカドなどに含まれる
また、甘いもの・カフェイン・アルコールは体を冷やしたり自律神経を乱す原因にもなるため、摂りすぎに注意しましょう。
軽めの運動を習慣にする
激しい運動は必要ありません。ゆったりした運動で血流を促し、心と体をほぐすことが大切です。
- 朝のストレッチ
- 20分程度のウォーキング
- ヨガや深呼吸を取り入れたリラックス体操
運動によってセロトニン(幸せホルモン)が分泌され、気持ちが安定しやすくなるという効果もあります。無理せず「気持ちよく終われる程度」が続けるこつです。
睡眠環境を整える
更年期には不眠や中途覚醒に悩む方も多く、睡眠の質を上げることが症状緩和につながります。
- 寝る前1時間はスマホやパソコンを控える
- 照明を落として、ゆっくりとした音楽や読書でリラックス
- 入浴はぬるめのお湯(38〜40度)で20分程度
- ハーブティー(カモミールなど)で心を落ち着ける
「眠れない」ときは無理に寝ようとせず、まずは布団の中で深呼吸をしてみてください。
心を整える時間をつくる
更年期はホルモンの変化だけでなく、ライフステージの変化(子育ての終わり、親の介護、職場での立場の変化など)と重なり、心の揺らぎが出やすい時期です。
- 気持ちを紙に書き出して整理する
- 誰かと話す(専門家や信頼できる人)
- 「自分が嬉しい」と思える小さなことを日常に取り入れる
- 無理に頑張らない日をあえて作る
「頑張らないことを頑張る」のも、大切なセルフケアのひとつです。
小さなケアを、こつこつ積み重ねて
更年期は、体が変わるサイン。そして、今まで頑張ってきた自分に立ち止まる時間をくれる時期でもあります。
「きちんと食べる」「少し歩く」「5分だけでもぼんやりする」このような小さなセルフケアの積み重ねが、あなたの明日を少しずつ軽やかにしてくれるはずです。
まとめ
更年期は誰もが経験するライフステージの一つですが、その影響の程度は人によって異なります。自分に合った対策を取り入れ、無理をせず、必要に応じて専門医に相談しましょう。
更年期障害で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。更年期障害は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」
「しっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。
※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院のご案内

更年期障害による気分の落ち込みや不安感は、日常生活に大きな影響を与えます。症状がつらいと感じたら、一人で悩まず専門医に相談することが大切です。メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、患者様の心の健康を支えるために、専門的な診察と治療を提供しています。
当院は 土日祝日も診療 しており、赤坂駅や天神駅から徒歩圏内 とアクセスも良好です。仕事や家事で忙しい方も通いやすい環境を整えております。また、当日予約が可能 で、電話またはWEB予約 に対応しています。
更年期障害に伴う不調やメンタル面でのサポートが必要な方は、ぜひ当院までご相談ください。