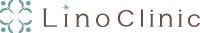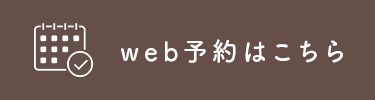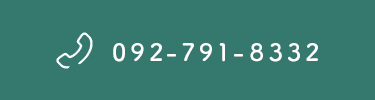睡眠障害や不眠症はどうすれば治る?原因と自力で治す方法まで解説

睡眠障害や不眠症は「眠りたいのに眠れない」「途中で目が覚めてしまう」など、日常生活に大きな支障をきたす深刻な悩みです。原因はストレスや生活習慣の乱れ、精神的な疾患などさまざまで、正しい対処が必要です。
本記事では、睡眠障害や不眠症の主な原因と治療法、さらに自宅でできるセルフケア方法まで詳しく解説します。睡眠に悩む方が安心して改善へ進めるヒントをお届けします。
不眠症の特徴
不眠症は、夜になっても寝つけない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目覚めてしまう、十分に寝たはずなのに疲れが取れないといった症状が続く睡眠障害の一つです。これらの症状は一時的に起こることもありますが、1ヶ月以上続くと慢性不眠症と診断されることがあります。
不眠症になると、ただ睡眠時間が短くなるだけではなく、睡眠の質自体が低下してしまいます。その結果、日中に強い眠気を感じたり、集中力が低下したり、イライラしやすくなったりするなど、生活全般に影響を及ぼします。また、体の免疫力が下がり、風邪をひきやすくなるなど健康面でもリスクが高まります。
原因はストレス、生活習慣の乱れ、精神的な疾患、身体的な病気などさまざまです。人によって現れ方が異なるため、早めに自分の睡眠状態を見直し、適切な対策を取ることが重要です。眠れない日が続くときは、一人で抱え込まず専門医に相談することをおすすめします。
睡眠障害や不眠症の治し方
「眠れない…」「夜中に何度も目が覚める…」そんなつらい不眠症や睡眠障害は、放置すると心身に大きな負担がかかります。原因に合わせた正しい治療を受けることで、少しずつ改善が期待できます。ここでは代表的な2つの治療法を紹介します。
薬物療法
薬物療法は、つらい不眠症状を一時的に和らげ、日中の生活への影響を軽減するために行われます。即効性が期待できるため、眠れないことによる強い不安や疲労がある方に使われることが多いです。
主に使われる薬には以下の種類があります。
-
睡眠薬(ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系)
寝つきを良くし、夜中に目が覚めるのを防ぐ効果があります。ただし、長期間使用すると依存や耐性が生じやすいため、短期間の使用が基本です。 -
抗不安薬
不安や緊張をやわらげることで、自然な眠りに導きます。ストレスや不安が強い場合に併用されることがあります。 -
メラトニン受容体作動薬
体内時計を調整し、自然な眠気を促す作用があります。高齢者や生活リズムが乱れがちな人に向いています。 -
オレキシン受容体拮抗薬
覚醒を促す「オレキシン」という神経伝達物質の働きを抑え、スムーズな入眠を助けます。近年注目されている新しいタイプの薬です。
薬の使用には、依存や副作用(ふらつき、記憶障害、翌朝の眠気など)のリスクが伴います。安全に使うためには、必ず医師の診察を受け、症状や体質に合わせて薬の種類や量を調整してもらうことが重要です。
「とりあえず薬に頼る」のではなく、生活習慣の改善や心理的アプローチと組み合わせて、根本的な改善を目指すことが大切です。決して自己判断での服用や急な中止はしないようにしましょう。
精神療法(認知行動療法)
不眠症の治療には、薬を使わない「精神療法」も非常に有効です。中でも代表的なのが「認知行動療法(CBT: Cognitive Behavioral Therapy)」です。
認知行動療法は、眠れないことへの過度な不安や「絶対に早く寝なければ」という思い込みなど、睡眠に対する誤った考え方(認知)と、それに伴う行動を見直していく治療法です。
具体的には、以下のような方法があります。
-
睡眠制限法
寝床にいる時間を制限し、眠気が強いときだけ布団に入るようにします。これにより、睡眠効率(寝床にいる時間に対して実際に眠れている割合)を高め、夜中の覚醒を減らします。 -
リラクゼーション法
深呼吸や筋弛緩法(体の筋肉をゆっくりと緩める方法)を取り入れることで、寝る前に心と体をリラックスさせ、自然な眠りに導きます。ストレスや緊張を和らげる効果があります。 -
認知の修正(認知再構築)
「眠れないと次の日に大失敗する」などの極端な思い込みを現実的な考えに変えていきます。過度な不安が軽減されることで、寝つきやすくなります。
この治療法の大きなメリットは、薬に頼らず根本的な改善を目指せることです。さらに、治療を通して身につけた新しい考え方や習慣は、再発防止にも役立ちます。
認知行動療法は専門の医師や心理士と一緒に進める方法が一般的ですが、最近ではオンラインプログラムやセルフワーク用の書籍などもあります。
「眠れない」という悩みを抱えたままにせず、自分の思考や行動を見直してみることで、より健やかな睡眠を取り戻せる可能性があります。
睡眠障害・不眠症のセルフケア方法

「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」などの不眠症や睡眠障害は、生活習慣の改善でも大きく変わることがあります。ここでは、今日から取り入れられるセルフケア方法を詳しくご紹介します。
朝起きて太陽の光を浴びる
朝の光には、体内時計(サーカディアンリズム)をリセットする役割があります。起きてすぐにカーテンを開けて太陽光を浴びることで、脳が「朝だ」と認識し、夜に自然な眠気を誘うメラトニンの分泌がスムーズになります。ベランダに出たり、軽く外を散歩するのも効果的です。
バランスの良い食事を摂る
睡眠と食事は密接に関係しています。特にマグネシウム(ほうれん草、アーモンド、大豆製品など)は神経の興奮を抑え、リラックスを促します。また、トリプトファン(卵、乳製品、バナナなど)を含む食材は、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になります。夜遅くの重い食事は避け、なるべく決まった時間に食べることも大切です。
日中に適度な運動をする
日中にウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど適度な運動をすることで、体のエネルギー消費が促され、夜の自然な眠気が強まります。ただし、寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激し逆効果になるので、寝る3時間前までに終えるのがおすすめです。
自分の睡眠を記録してみる
毎日の睡眠時間、寝つくまでの時間、夜中の目覚めの回数などをノートやアプリに記録してみましょう。記録を見返すことで、自分の睡眠リズムや改善すべき点がわかり、生活習慣の見直しにつながります。医師に相談する際の資料としても役立ちます。
ツボ押しをしてみる
ツボ押しは気軽にできるリラックス方法の一つです。「失眠(しつみん)」というツボは足の裏のかかと付近にあり、安眠を促すといわれています。また、手の「労宮(ろうきゅう)」や「内関(ないかん)」もおすすめです。強く押しすぎず、痛気持ちいい程度に数秒ずつ押すのがポイントです。
深呼吸や瞑想をする
深呼吸や瞑想は、自律神経を整え、心と体をリラックスさせる効果があります。布団に入った後、4秒かけて息を吸い、7秒止め、8秒かけて吐く「4-7-8呼吸法」などがおすすめです。寝る前に頭を空っぽにして心を静める時間を作ることで、寝つきがよくなります。
入浴やアロマを使いリラックスする
就寝1〜2時間前のぬるめのお風呂(38〜40℃)に10〜20分ほど浸かると、入浴後に体温が下がるタイミングで眠気が訪れやすくなります。ラベンダーやカモミールなどのアロマオイルを使えば、さらにリラックス効果が高まります。アロマは枕元に垂らす、ディフューザーで焚くなどお好みで取り入れてみてください。
寝室の環境を整える
静かで暗い、適度な温度と湿度が保たれた寝室環境は、質の高い睡眠に不可欠です。寝具の硬さや枕の高さを見直し、寝室を整理整頓することで心理的にもリラックスできます。遮光カーテンや加湿器の利用もおすすめです。
就寝前に水分やカフェインを摂らない
寝る直前のカフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)は脳を刺激し、眠りを妨げます。また、過剰な水分摂取は夜中にトイレに起きる原因になるため、寝る2時間前からは水分を控えめにするのがポイントです。
お酒やタバコを控える
お酒は寝つきを良くするように感じるかもしれませんが、睡眠の後半に浅い眠りを引き起こし、中途覚醒を増やします。タバコに含まれるニコチンも覚醒作用があり、睡眠の質を低下させます。健康面でも大きな負担になるため、できるだけ控えましょう。
睡眠障害・不眠症の主な4つのタイプと特徴

睡眠障害や不眠症と一口に言っても、症状にはさまざまなタイプがあります。自分がどのタイプに当てはまるのかを知ることは、適切な対策や治療を選ぶ第一歩です。ここでは代表的な4つのタイプとその特徴を紹介します。
入眠障害
入眠障害は「布団に入ってもなかなか寝つけない」という状態を指します。一般的には、寝床に入ってから30分以上眠れない状態が続くと入眠障害とされます。
原因の多くは、ストレスや緊張、不安感です。「眠れなかったらどうしよう」というプレッシャー自体が、さらに脳を活性化させてしまい、悪循環を招きます。また、スマートフォンやパソコンなどの強い光(ブルーライト)は脳を覚醒させるため、夜遅くまでの使用は入眠を妨げる原因になります。
対策としては、就寝前のルーティンを決めることが効果的です。ぬるめのお風呂に浸かる、温かい飲み物(カフェインを含まないハーブティーなど)を飲む、軽いストレッチや深呼吸を行うなど、心と体を「眠りモード」に切り替える習慣を取り入れることが大切です。
中途覚醒
中途覚醒は、寝つけても夜中に何度も目が覚めてしまうタイプの不眠症です。加齢とともに増加しやすく、特に高齢者に多く見られます。また、精神的ストレス、うつ病、睡眠時無呼吸症候群、頻尿など身体的要因が関わっている場合もあります。
中途覚醒が頻繁にあると、睡眠のサイクルが乱れて深い睡眠(ノンレム睡眠)が減り、翌日の疲労感が強くなります。「夜中に目が覚めたら時計を見ない」「再び眠れなくても無理に寝ようとせず、一度リラックスする」などの対応が重要です。
寝室の環境(温度、湿度、光、音)を整え、夜間にトイレへ行く回数を減らすために就寝前の水分摂取を控えることも効果的です。
早朝覚醒
早朝覚醒は「まだ起きる時間ではないのに目が覚めてしまい、その後眠れない」という状態を指します。特にうつ病が関係していることが多く、症状の一部として現れる場合があります。また、高齢になると体内時計の変化により、早寝早起きのリズムに変わるため自然と早朝覚醒が起こりやすくなります。
朝早く目覚めることで、十分に睡眠をとったつもりでも昼間に強い眠気や集中力の低下、体のだるさを感じることが多くなります。
対策としては、朝日を浴びる時間をコントロールし、体内時計を調整することが大切です。また、夜間に気持ちを落ち着けるためにリラックス習慣を持つ、夜遅くまでテレビやスマホを見ないといった生活リズムの見直しが重要です。
熟眠障害
熟眠障害は「眠れたはずなのに熟睡感がない」「朝起きても疲れが取れていない」と感じるタイプの不眠症です。睡眠時間が十分でも、睡眠の質が低下しているのが特徴です。
原因には、加齢、ストレス、過剰なアルコール摂取、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群などが関わることがあります。深い眠りが少なくなると、体や脳の修復が不十分になり、日中の倦怠感、注意力低下、気分の落ち込みなどを引き起こします。
対策としては、規則正しい生活リズムを保つ、睡眠環境を整える、寝る前にリラックスする時間を確保するなど、質の高い睡眠を目指す習慣づくりが必要です。
また、日中の過度な昼寝を控え、必要なら15〜20分程度の短時間にとどめると、夜の睡眠に影響しにくくなります。
睡眠障害・不眠症になってしまう主な5つの原因

睡眠障害や不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、心身のさまざまな問題が関係しています。原因を知ることで、改善のヒントが見つかります。ここでは代表的な5つの原因をご紹介します。
ストレスの要因
仕事、家庭、人間関係、将来の不安など、現代社会では常にストレスにさらされています。ストレスが続くと自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になり、リラックスできずに眠れない状態に陥ります。
「明日大事な会議があるから寝なければ」と考えるほど逆効果になることもあります。ストレスが原因の場合、寝る前にリラックスできる時間を確保したり、深呼吸、軽いストレッチ、アロマテラピーなどで心身を落ち着けることが重要です。
精神的な疾患
うつ病、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患は、不眠症と深い関係があります。例えば、うつ病では「早朝覚醒」が多く見られますし、不安障害では入眠障害がよく見られます。
精神的な疾患が背景にある場合は、セルフケアだけでは改善が難しく、専門医による診察や治療が必要です。放置すると症状が悪化する可能性があるため、早めの相談が大切です。
生活習慣の乱れ
夜更かし、昼夜逆転、不規則な食事、運動不足など、生活リズムの乱れは睡眠障害の大きな原因です。特に、寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトが脳を刺激し、メラトニンの分泌を抑えてしまいます。
夕食が遅い、夜遅くまでカフェインを摂る、休日に長時間寝すぎるといった生活も、体内時計を狂わせます。規則正しい生活リズムを保ち、なるべく毎日同じ時間に起床・就寝することが大切です。
アルコールや薬物の使用
「お酒を飲めば眠れる」というイメージを持つ方が多いですが、実際はアルコールが深い睡眠を妨げ、夜中に目が覚めやすくなる原因になります。
また、タバコに含まれるニコチンや一部の薬物は覚醒作用があり、寝つきを悪くしたり、睡眠の質を低下させます。寝酒や喫煙が習慣化すると、徐々に依存症状が現れるリスクもあります。長期的に見れば、アルコールや薬物に頼らず自然な眠りを取り戻す努力が必要です。
身体的な疾患
慢性的な痛み(腰痛、肩こり、関節痛など)、呼吸器疾患(喘息、睡眠時無呼吸症候群)、アレルギー、皮膚のかゆみ、胃腸の不調、ホルモンバランスの乱れなど、身体的な疾患が睡眠を妨げることがあります。
例えば、夜中に咳が出る、息苦しくなる、トイレに何度も起きるなどの症状があると、睡眠の中断が増えて十分に休めません。
この場合は、基礎疾患の治療を進めることが最優先です。気になる体調の変化がある場合には、早めに専門医に相談し、原因を特定することが重要です。
不眠症が突然治ることはある?

「ある日を境に急に眠れるようになった」という話を耳にすることがありますが、実際には非常にまれです。
一時的にストレスの原因が解消したり、疲れがピークに達した結果、たまたまぐっすり眠れる日があることはあります。しかし、根本的な原因(ストレス、生活習慣、精神的・身体的な疾患など)が解決されていない場合、再び不眠症の症状が戻ってくる可能性が高いです。
不眠症は慢性化しやすいため、「突然治る」ことを期待するよりも、医師による適切な治療と生活習慣の見直し、セルフケアを継続することが大切です。
まとめ
不眠症や睡眠障害は、多くの方が悩む身近な問題です。
原因はストレス、精神的な疾患、生活習慣の乱れ、アルコールや薬物の影響、身体的な病気などさまざまですが、正しい治療とセルフケアで改善が期待できます。
「眠れない」「朝スッキリ起きられない」など、少しでも不安があれば専門家に相談してみてください。
不眠症で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。不眠症は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」 「しっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院でのサポート
自閉スペクトラム症の特性によって、日常生活に困難を感じることがあるかもしれません。しかし、適切なサポートや環境調整によって、より快適な生活を送ることが可能です。メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、不眠症に関する診察を行っており、専門の医師が一人ひとりに合った対応策を提案します。赤坂駅や天神駅から徒歩圏内でアクセスが良く、土日祝日も診療しているため、仕事や学校の合間にも通院が可能です。まずはお気軽にご相談ください。あなたに合った最適な支援を一緒に考えていきましょう。