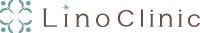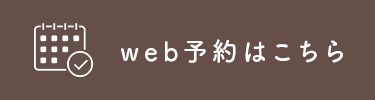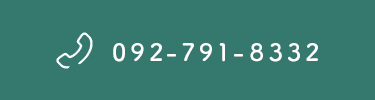双極性障害(躁うつ病)とは?

毎日の生活の中で、気分の浮き沈みを感じることは誰にでもあり得るこ とです。しかし、その変動が極端で、生活に支障を来すほど激しい場合は「双極性障害(躁うつ病)」の可能性があります。
双極性障害は、躁状態(気分が異常に高揚する状態)と、
うつ状態(気分が極端に落ち込む状態)を繰り返す精神疾患で、
適切な治療とサポートが必要です。
もし
「最近気分の変動が激しくてつらい…」
「うつの時期と元気すぎる時期を繰り返している…」
と感じている方がいたら、決して一人で抱え込まないでください。
双極性障害は、治療により症状をコントロールできる病気です。
今回は、双極性障害の特徴や原因、治療法について詳しく解説していきます。
双極性障害の基本的な特徴

双極性障害(躁うつ病)は、気分の極端な変動を特徴とする精神疾患です。
本人の意思とは関係なく、「躁状態」と「うつ状態」という正反対の気分が周期的に繰り返されるのが特徴です。
躁状態(ハイな気分)
躁状態は「元気過ぎる」「ハイテンション」の状態です。以下のようなサインが見られます。
- 気分が異常に高揚し、活動的になる
普段よりもテンションが高く、話し方や行動が早くなることが多いです。
- 睡眠時間が短くても元気に動き回れる
3~4時間しか寝ていなくても、全く疲れを感じずに動ける状態が続きます。
- 自信過剰になり、無謀な行動をとることがある
「自分は何でもできる」と感じて、根拠のない自信を持ち過ぎてしまうことがあります。
- 次々にアイデアが浮かんでくる、おしゃべりになる
新しいアイデアが瞬時に浮かんだり次々と言葉が出てきたりするようになる傾向です。
- お金を浪費したり、突発的な行動が増えたりする
高額な買い物やギャンブル、急な旅行・仕事の辞職など、日常では考えにくい行動をとってしまう場合があります。
- 性的逸脱行動が見られる
通常、本来のその人なら絶対にしないような性的な行動や言動(複数人との関係、露出、性的言動の公言など分別のつかない行動)が見られる場合があります。
一見「調子が良い」ように見えても、周囲とのトラブルや本人の生活に悪影響を及ぼすことが多く、治療が必要な状態です。本人には病気という自覚がなく、むしろ「これが本来の自分だ」「すべてうまくいっている」と思っている傾向があります。
うつ状態(気分の落ち込み)
うつ状態は、躁状態とは反対に強い落ち込みが続く状態です。うつ病の症状によく似ており、以下のようなサインが見られます。
- 強い憂うつ感や無気力を感じる
何をするにも気力が湧かず、何も手につきません。布団から出られないような状態が続くこともあります。
- 何をしても楽しくない、興味が持てない
以前は好きだった趣味や人付き合いにも興味が持てなくなり、感情が乏しくなる傾向があります。
- 自分に価値がないと感じる
罪悪感が強くなり、生きる価値がないと自分を責め続けてしまいがちです。
- 集中力が低下し、仕事や日常生活が困難になる
ミスが増えたり、話の内容が頭に入らなくなったりするなど、思考力・判断力が落ちてしまいます。
- 倦怠感や疲れやすさ、頭痛、肩こりなど身体に不調が出る
体がだるい、疲れやすい、頭痛、肩こり、動悸、胃の不快感、便秘、下痢、めまいなどさまざまな身体症状が現れます。
- 睡眠障害(過眠または不眠)、食欲の変化
寝すぎてしまう、眠れなくなる、食べ過ぎ・食欲不振、飲酒量の増加といった睡眠や食事に関する変化も多いです。
- 死を考えるようになる
「死にたい」「消えてしまいたい」「遠くへ行きたい」など死を身近に考えるようになります。
このようなうつ症状のある期間は、病気の期間のおおよそ3~5割程度を占めるといわれており、本人は大変つらい状態です。躁状態とのギャップがあり周囲は戸惑うかもしれませんが、そっと見守ることが必要です。
この2つの状態が周期的に繰り返されるのが双極性障害
- 気分が高揚してエネルギーがあふれる「躁状態」と、
- 気分が落ち込み何も手につかない「うつ状態」
これらの波が数週間から数か月単位で入れ替わるのが、双極性障害の大きな特徴です。
一見すると「元気なとき」と「疲れているとき」があるように見えるため、周囲にも本人にも気づかれにくいことがあります。
混合状態
双極性障害では、躁状態とうつ状態が明確に分かれて現れるだけでなく、同時に現れることがあります。これを「混合状態」といい、気分・思考・意欲といった要素がそれぞれ異なる方向に働いている状態です。例えば、気分は沈んでいるのに行動は活発だったり、興奮して早口で話し続けているのに突然涙を流したりするなど、精神状態と行動が一致しないことが特徴です。
混合状態は、うつ状態から躁状態、またはその逆への移行期や、抑うつ状態にある方に抗うつ薬を使用したときにも生じやすいといわれています。特にうつ状態の中で行動が躁状態になっているケースでは、自殺リスクが高まる可能性があるため、注意が必要です。
双極性障害とうつ病の違い
双極性障害は、かつて「躁うつ病」と呼ばれていたため、うつ病の一種と誤解されることがありますが、実際には異なる病気です。うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下、不眠などのうつ症状のみが見られるのに対し、双極性障害は躁状態とうつ状態という正反対の状態を周期的に繰り返すのが特徴です。
明らかな躁状態で受診すれば双極性障害という診断がされますが、うつ状態で受診した場合はうつ病と診断されることもあります。特に、躁状態では本人はとても好調だと感じているため病院を受診しなかったり、周りが声掛けをしても受診を拒否したりする傾向が見られます。
治療の方向性にも違いがあり、うつ病はうつ症状を軽減する治療が中心ですが、双極性障害では躁状態とうつ状態の波を小さくすることが治療の目的です。うつ病と判断されてしまうことで適切な治療が受けられないと、かえって症状の悪化や長期化につながる可能性があるため、慎重な診断が求められます。
双極性障害の2つのタイプ

双極性障害は、症状の現れ方によって「双極Ⅰ型障害」と「双極Ⅱ型障害」の2つに分けられます。
それぞれのタイプには特徴的な違いがあり、治療方針やサポートの方法も異なるため、正確な診断がとても重要です。
① 双極Ⅰ型障害
躁状態が非常に激しく、日常生活や社会生活に深刻な影響を及ぼすタイプです。
- 躁状態では、異常なほど気分が高揚し、自信過剰や過活動が顕著に現れます。
- 睡眠時間がほとんどなくても疲れを感じず、延々と話し続けたり、止まらない行動を繰り返したりします。
- 金銭感覚の麻痺(衝動買い・浪費)や性的逸脱行動、攻撃的な言動などが見られ、人間関係や社会的信用に大きなダメージを与えることもあります。
- 症状が悪化すると、現実感を失い幻覚や妄想が現れる「躁病性精神病」に至るケースもあります。
特に、躁状態のピーク時には自傷行為や事故のリスクも高まるため、専門的な管理が必要です。
そのため、重度の躁状態にある場合には、医師の判断で入院治療が選択されることもあります。
② 双極Ⅱ型障害
軽躁状態とうつ状態を繰り返すタイプで、Ⅰ型に比べて躁の程度は穏やかですが、うつ状態が深く長引く傾向があります。
- 軽躁状態では、元気になったり社交的になったりするものの、明らかな問題行動には至らないケースが多いです。
- 一見「調子がいい」「働きすぎかな」と思われることもあり、周囲からも見逃されやすい特徴があります。
しかし、その後に続くうつ状態は深刻で、以下のような問題が起こることがあります。
- 無気力感や強い自己否定感が長期間続く
- 過眠や食欲不振などの身体症状が強く出る
- 「死にたい」と感じるほどの抑うつが生じることもあり、自殺リスクが高まるケースも
双極Ⅱ型は、うつ症状が中心であるため、うつ病と誤診されることも少なくありません。
その結果、適切な治療が遅れ、症状が慢性化するリスクもあります。
そのため、軽躁状態のエピソードを見逃さず、症状の経過を丁寧に伝えることが診断のカギとなります。
タイプにかかわらず大切なこと
双極性障害はいずれのタイプであっても、気分の波を自分の意思でコントロールするのが難しい病気です。
しかし、適切な診断と治療、周囲の理解と支えがあれば、症状をコントロールしながら安定した生活を送ることができます。
自身の気分の変化に気づいたら、早めに心療内科や精神科へ相談することをおすすめします。
双極性障害の原因

双極性障害は、誰にでも起こり得る可能性のある精神疾患ですが、現在の医学ではその明確な発症原因はまだ完全には解明されていません。
しかし、多くの研究から、複数の要因が複雑に関係していることが分かっています。ここでは、主に関与しているとされる3つの要素をご紹介します。
① 遺伝的要因(家族内発症の傾向)
双極性障害は、同じ家族の中で発症するケースが比較的多いことが知られており、遺伝的な要素が関係していると考えられています。
- 両親や兄弟姉妹に双極性障害の既往がある場合、一般的な人よりも発症リスクが高くなる傾向があります。
- 特に、一卵性双生児の研究においては、一方が発症すると他方も発症する確率が高いことが示されており、遺伝との関連性が注目されています。
ただし、重要なのは、遺伝要因だけで発症が決まるわけではないということです。
実際には、遺伝的な体質に加えて、その人の環境やストレス状況が合わさることで発症リスクが高まると考えられています。
② 脳内の神経伝達物質の異常
双極性障害は、脳内の神経伝達物質(神経細胞同士の情報をやりとりする化学物質)のバランスが乱れることと強く関係していると考えられています。
特に注目されているのは、次の3つの物質です:
- セロトニン: 気分や感情の安定に関わる
- ドーパミン: 快楽・意欲・報酬系の調整に関わる
- ノルアドレナリン: ストレス反応や警戒心の調整に関わる
これらの物質が過剰または不足している状態になると、気分の高揚(躁状態)や落ち込み(うつ状態)といった症状が生じやすくなります。
そのため、治療においては、これらの神経伝達物質のバランスを整える薬が使用されることが多いです。
③ 環境要因・ストレス(生活背景の影響)
双極性障害は、生活の中でのストレスや環境の変化が発症や再発の引き金になることが多いとされています。
以下のような体験が、脳や心に強い負荷をかけ、潜在的なリスクを持っていた人に発症を引き起こすことがあります。
- 家庭や職場での強いストレス(プレッシャー、過労など)
- トラウマ体験(事故・暴力・虐待など)
- 大きな生活の変化(転職、引っ越し、出産、離婚、受験など)
- 人間関係のトラブル(孤立、いじめ、親密な関係の断絶など)
また、ストレスがなくなった後に発症する「反動」のようなケースもあるため、単純に「原因を取り除けば治る」というわけではありません。
むしろ、ストレスの捉え方や対応力、サポート体制の有無が大きく影響すると考えられています。
原因は「ひとつだけ」ではありません
双極性障害は、体質(遺伝)・脳の状態・環境的なきっかけなどが重なり合って発症する病気です。
「これが原因」と特定することは難しいですが、原因を理解することは、再発予防や周囲の理解にもつながります。
自分を責めたり、過去の出来事を後悔したりする必要はありません。
症状に合わせて、安心できるサポートや治療を見つけていくことが、回復への一歩になります。
双極性障害の診断

双極性障害は、うつ状態と躁(または軽躁)状態を繰り返すことが特徴ですが、その症状は他の精神疾患と似ている部分も多く、正確な診断には専門的な判断が必要です。
特に重要なのが、精神科医による丁寧な問診(診察)です。ここでは、診断の流れと注意点について詳しく解説します。
1. 問診と症状のヒアリングが中心
診断では、まず医師が患者本人の現在の症状だけでなく、過去の気分の変化や行動の特徴を丁寧に聞き取ります。
- これまでに気分が高揚しすぎた経験(躁または軽躁状態)がなかったか
- 落ち込みのエピソード(うつ状態)がどれくらいの頻度・期間で続いているか
- 睡眠、食欲、行動パターン、人間関係への影響なども詳しく確認されます
双極性障害は、うつ状態が先に現れることが多く、最初はうつ病と診断されるケースも珍しくありません。
そのため、過去に「数日間ほとんど寝なくても元気に動き続けたことがある」「妙に自信過剰になって普段しない行動をとった」などのエピソードが過去にあったかを思い出すことが重要です。
本人は「少し調子が良かっただけ」と感じていても、それが軽躁状態や躁状態のサインであることがあります。
2. 双極性障害と他の疾患との鑑別(見分け)が必要
双極性障害は、以下のような他の精神疾患と症状が似ているため、慎重な見極めが求められます。
- うつ病(大うつ病性障害)
- 不安障害・パニック障害
- 発達障害(ADHDなど)
- パーソナリティ障害
特に、前述のようにうつ状態のときに受診し、躁状態について伝えない場合、うつ病と診断されてしまうことも多いです。そのため、似た症状を呈する病気との違いを明確にするため に、医師は長期的な症状の経過や、周囲の情報(家族や支援者の話)も参考にします。必要に応じて、心理検査やスクリーニングツールを用いることもあります。
3. 診断には「時間」が必要なことも
双極性障害の診断は、一度の受診だけでは判断が難しいこともあります。
特に、軽躁状態は「本人が異常と感じない」ことが多く、医師に正しく伝わらないことがあるため、数回の診察や経過観察が必要になる場合もあります。
また、気分の波が年に数回しか起こらないケースもあり、その場合は診断確定までにある程度の時間をかけて慎重に見ていくことが大切です。
双極性障害の治療法

双極性障害は、適切な治療を受けることで、気分の波を安定させ、日常生活を安心して送ることが可能な病気です。
治療は、主に「薬物療法」「心理療法」「生活習慣の改善」の3つを組み合わせて行います。
1. 薬物療法(もっとも中心となる治療)
■ 気分安定薬(リチウムなど)
- 気分の波を抑える働きがあり、躁状態・うつ状態の両方に有効です。
- 双極性障害の第一選択薬として広く使われており、再発予防にも効果が期待できます。
- 一定の効果を保つには血中濃度の管理が必要なため、定期的な採血や診察を受けることが大切です。
- 主な薬:リチウム、ラモトリギン、バルプロ酸など
■ 抗精神病薬(躁状態に対応)
- 強い興奮や衝動性、妄想的な思考を抑えるために使用されます。
- 特に躁状態が激しい場合や、入院治療が必要なケースで用いられることが多いです。
- 一部の抗精神病薬は、うつ状態にも効果があるとされ、補助的に処方されることもあります。
- 副作用(眠気、体重増加、筋肉のこわばりなど)が出ることがあるため、医師の管理下で慎重に使用します。
■ 抗うつ薬(うつ状態に対応)
- うつ状態を改善するために処方されますが、躁状態へ移行する「躁転」のリスクがあります。
- そのため、抗うつ薬は単独では使われず、必ず気分安定薬と併用されるのが原則です。
- 効果や副作用の出方には個人差があるため、少量から始めて慎重に調整していきます。
2. 心理療法(気分の波を予防・緩和するためのサポート)
■ 認知行動療法(CBT)
- 思考のクセや偏りに気づき、気分の浮き沈みに左右されない考え方を育てます。
- また、ストレスに対処する技術や、再発を防ぐための行動パターンを学びます。
■ 対人関係療法
- 人間関係のストレスがきっかけとなって症状が悪化する方に有効です。
- 周囲との付き合い方を見直し、安定した生活リズムを築くための関係性を整えていきます。
心理療法は、薬では補えない「心の整え方」を学ぶ重要な治療の柱です。
医師や臨床心理士とともに、安心できるペースで進めていくことが大切です。
3. 生活習慣の改善(日々の安定のためにできること)

双極性障害の再発を防ぐためには、生活リズムを整えることが非常に重要です。
- 規則正しい生活を意識する(毎日同じ時間に寝起きするなど)
- 睡眠の質と量を安定させる(寝すぎも寝不足も避ける)
- 適度な運動を継続する(ウォーキングやストレッチなど軽いものでOK)
- 過度なストレスを避け、自分に合ったリラックス法を見つける(趣味・音楽・入浴など)
生活習慣の安定は、薬や心理療法の効果を高め、再発の予防にもつながる大切な土台となります。
(出典:すまいるナビゲーター 双極性障害とは – 原因、症状、治療方法などの解説)
双極性障害治療の心構 え
双極性障害の治療には、本人だけでなく、周囲や家族の正しい理解と継続的なサポートが欠かせません。ここでは、治療に向き合う上で大切な心構えをいくつかご紹介します。
病気を受け入れて治療を継続する
まず、双極性障害の症状を受け入れて、継続的に治療をしていくことが大切です。双極性障害の診断を受けたとき、戸惑ったり否定的な気持ちになったりするかもしれません。「時間が経てば治るだろう」「薬を飲めばすぐに回復するはずだ」と症状を軽視してしまうこともあるでしょう。
しかし、治療をおろそかにしたり、自己判断で服用をやめてしまったりすると、再発のリスクが高くなります。症状を受け入れ、医師の指示に従いながら、根気よく治療に向き合うようにしましょう。
発症の原因を振り返ってみる
双極性障害を発症した原因を振り返ってみることも大切です。発症の原因は一つに特定できるものではなく、明確に解明されていませんが、発症時にどのような出来事があったかを振り返ることで、ストレスを感じやすい傾向や環境に気付ける場合があります。自身のストレス傾向を知ることで予防策が取れるようになり、再発防止にも役に立つでしょう。
再発のサインを周囲や家族と共有する
再発のサインを周囲や家族と共有しておくと、早期に対処できるため再発や重症化の予防になります。例えば、睡眠時間が短くなる、活動量が増える、話が止まらなくなるなど、人によって再発のサインがあるはずです。そうしたサインを周囲や家族が認識しておけば、少しでも変化が見られた際に、早めに主治医に相談することができます。
焦らずに回復を目指す
双極性障害の治療は、長期にわたることが多いことを認識しておくことも大切です。症状が安定していても、薬の服用を継続し、毎日の生活リズムを崩さないようにしましょう。「もう薬は飲みたくない」と感じても自己判断で中止せず、必ず主治医へ相談してください。焦らず、自分のペースで回復を目指すことが、より良い状態につながります。
家族だけで抱え込まないために
双極性障害の治療において、家族のサポートは大きな役割を果たします。しかし「家族の問題だから」といって、誰にも頼らず無理をしてしまうと、サポートする側の心身に大きな負担がかかってしまいます。ここでは家族だけで抱え込まないためにはどうすれば良いかをお伝えします。
家族がゆとりを持つことを意識する
患者さんを支える家族こそ、心に余裕を持つことが重要です。家族が心身ともに安定して過ごしていることは、患者さんにも良い影響を与えます。時には自分自身のための時間を確保し、趣味を楽しんだり、友人と会って話したりするなど、リフレッシュする時間をつくりましょう。
また悩みや不安を抱えたときは、親族以外の信頼できる人に相談してみるのも良い方法です。「つらい」「しんどい」と感じたときには、無理をせず心身が健康でいられる状態を保ちましょう。
支援ネットワークや相談窓口を活用する
地域によっては、行政や医療機関が設けている相談窓口で、精神保健福祉士や看護師などの専門スタッフが対応してくれます。また同じ経験を持つ家族とつながれる「家族会」や、支援団体などさまざまなネットワークも存在します。かかりつけの医療機関、地域の保健所、精神保健福祉センターの他にも、困ったときに相談したり同じ悩みを共有したりできる場所があると、孤独感を軽減できます。より良い関係性を築くヒントが得られることもあるでしょう。
例えば、以下のような相談窓口・支援ネットワークがあります。必要に応じて利用してみると良いでしょう。
● 「こころの健康相談統一ダイヤル」(厚生労働省)
お住まいの地域の心の健康電話相談窓口や、公益社団法人日本精神保健福祉士協会、公益社団法人日本公認心理師協会に電話を転送し、専門スタッフが対応してくれます。(電話番号:0570-064-556)
● 「みんなねっと相談室」(公益社団法人全国精神保健福祉会連合会)
精神疾患のある家族についての悩みを電話で相談できます。(電話番号:03-5941-6346)
● 「みんなねっとサロン」(公益社団法人全国精神保健福祉会連合会)
同じ悩みを抱える家族同士が交流できるオンラインコミュニティ。情報交換や気持ちの共有ができます。
● NPO法人ノーチラス会(特定非営利活動法人日本双極性障害団体連合会)
双極性障害の当事者や家族を支援する団体で、講演会やレクリエーションも実施しています。
まとめ
双極性障害(躁うつ病)は、気分が極端に高揚した躁状態と、極端に落ち込んだうつ状態を繰り返す精神的な障害です。躁状態ではエネルギーが過剰になり、判断力が低下して無謀な行動をとることがあります。反対に、うつ状態では深い悲しみや無気力、社会的な孤立感が強くなります。
双極性障害は、早期の診断と適切な治療が重要です。薬物療法や精神療法を組み合わせることで、症状を管理し、生活の質を改善することにつながります。定期的な医師のサポートを受けながら、症状の波を乗り越えていきましょう。
双極性障害(躁うつ病)で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。双極性障害(躁うつ病)は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」
「しっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケアLino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
双極性障害のご相談はLino clinicへ

メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)では、双極性障害の診断・治療を行っており、患者さま一人ひとりに寄り添ったサポートを大切にしています。
📍 アクセスしやすい立地 → 赤坂駅・天神駅から徒歩圏内
🕗 土日祝も夜8時まで診療 → 忙しい方でも通いやすい
📅 当日予約可能 → お電話またはWEBでスムーズに予約
「少しでも早く相談したい」「自分の状態を知りたい」と感じたら、ぜひLino clinicへご相談ください。あなたが安心して治療に向き合えるよう、スタッフ一同サポートいたします。