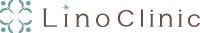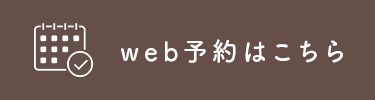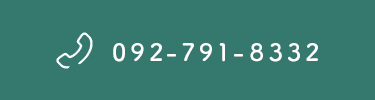強迫性障害とは?

毎日の生活の中で、「鍵を閉めたか不安になる」「手の汚れが気になって何度も洗う」といった経験は誰にでもあるでしょう。しかし、その不安や行動が極端に強くなり、日常生活に支障を来すほど繰り返してしまう場合、それは「強迫性障害(OCD)」の可能性があります。強迫性障害は、「不安を引き起こす強迫観念」と「その不安を和らげるための強迫行為」が特徴の精神疾患です。本人は「やめたい」と思っていても、不安に駆られて同じ行動を繰り返してしまうため、生活の質が著しく低下します。
もし、「どうしても気になってしまい、何度も確認してしまう……」「この行動をしないと落ち着かない……」と悩んでいるなら、決して一人で抱え込まないでください。強迫性障害は、適切な治療を受けることで症状を和らげ、日常生活を取り戻すことができます。今回は、強迫性障害の特徴や原因、治療法について詳しく解説していきます。
強迫性障害とは?
強迫性障害(Obsessive-Compulsive Disorder, OCD)は、「強迫観念」と「強迫行為」を繰り返す精神疾患です。
強迫観念(Obsessive Thoughts)
強迫観念とは、不合理であると自覚していても、頭から離れない考えやイメージが湧くことです。例えば、「手が汚れているのではないか」「火を消し忘れたかもしれない」といった疑念や、「不吉なことが起こるのではないか」といった恐怖に繰り返し襲われます。これらの思考は、本人の意志とは無関係に何度も浮かぶため、強い不安や苦痛を感じてしまうのが特徴です。周囲から見ると取るに足らないことでも、本人にとっては極めて深刻な問題に感じられ、日常生活に大きな支障を来します。
強迫行為(Compulsive Behaviors)
強迫行為とは、強迫観念による不安を軽減するために繰り返し行ってしまう行動や儀式的な動作のことです。例えば、手を清潔に保つために何度も手を洗ったり、鍵を閉めたことを何度も確認したりすることがあります。これらの行為は一時的に不安を和らげるものの、長期的には強迫観念を強化し、行動の頻度や時間が増えてしまうことも少なくありません。本人も無意味だと分かっていてもやめられず、日常生活や社会生活に影響を及ぼします。
心配症や潔癖症との違い
強迫性障害は、心配性や潔癖症とは明らかに異なる精神疾患です。例えば、心配性の方が「火を消したかな?」と気になるのはよくあることですが、強迫性障害の方はその不安が頭から離れず、何度も確認を繰り返さずにはいられません。潔癖症のように「きれいにしたい」という気持ちから掃除するのではなく、「汚れているかもしれない」という強い不安に駆られて行動するのが特徴です。
強迫性障害を患うと、本人がその不安や行動が行き過ぎていることに気づいていながら、自分の力ではやめられずに苦痛を感じ、学業、仕事、人間関係などの日常生活に大きな支障が出てしまいます。このように、強迫性障害は性格の問題ではなく、適切な治療を受けるべき病気です。
強迫性障害の主な症状

強迫性障害では、いくつかの傾向的な症状が見られます。代表的な例を紹介します。
① 汚染・不潔に対する恐怖
- 例:「手が汚れているかも」「ウイルスがついているかも」と不安になり、何度も手を洗う
- 外出後やトイレ使用後に極端に長い時間をかけて手洗いをする
② 確認行為
- 例:「鍵を閉めたか」「火を消したか」と何度も確認する
- 仕事の書類やメールを過剰にチェックしないと安心できない
③ 加害恐怖
- 例:「自分が誰かを傷つけてしまうのでは?」と不安になる
- 道を歩いていて「今、誰かにぶつかってけがをさせたかも」と振り返る
④ 数字や順番へのこだわり
- 例:「特定の数字でないと不吉なことが起こる」と感じる
- 決められた回数で行動しないと気が済まない
⑤ 宗教的・道徳的な強迫観念
- 例:「罪悪感が強過ぎて、何度もお祈りしないと安心できない」
強迫性障害になりやすい人の特徴

強迫性障害は、明確な原因が分かっているわけではありませんが、いくつかの傾向は指摘されています。例えば、几帳面で完璧主義、責任感がある、こだわりが強い、融通が利かないといった性格の人は、仕事や人間関係でのストレスを感じやすく、それが発症のきっかけになることがあります。
また、家族に同じ精神疾患を持つ人がいる場合や、過去に神経の病気や特定の感染症を経験したことがある場合も、発症しやすいケースです。さらに、結婚や妊娠・出産、離婚、転職、引っ越しなど、ライフイベントや生活環境の変化が引き金になることもあります。
あくまでも「なりやすさの傾向」であり、誰でも発症する可能性がある点は理解しておきましょう。
強迫性障害かな?と感じたときの受診目安

日常の中で不安やこだわりを感じるのは誰にでもあることですが、それによって生活や人間関係に支障が出ている場合は、強迫性障害の可能性があるかもしれません。
例えば、手洗いや戸締まり確認に過剰な時間を使い、家事や仕事、睡眠に影響が出ている場合です。また、スケジュールを守れない、決まった順番で物を並べないと落ち着かず強要するなど、周囲の人が困惑するようなケースが繰り返される場合も注意が必要です。
本人もこれらの行動が「無意味で過剰だ」と分かっていながら止められず、苦痛を感じている場合には早めの受診が推奨されます。
強迫性障害の方は、強迫観念が出てきても、強迫行為によって一時的に安心を得られるため、やり過ごせてしまいがちです。そのため、症状が進行してから受診する方も多いですが、悪化すると治すのにも時間と労力がかかるため、一人で抱え込まずに、気になる症状があれば心療内科や精神科、メンタルクリニックに相談することが大切です。
強迫性障害の重症度診断表

強迫性障害は、血液検査や画像検査などの目に見える診断によって病名が特定されるわけではありません。症状の程度や日常生活への影響度など、総合的に評価して診断されます。
医療機関では以下のようにいくつかの評価尺度が使われており、目的によって使い分けたり組み合わせたりして活用されます。
- Y-BOCS(イェール・ブラウン強迫スケール):強迫症の重症度を評価する
- MOCI(マウドスリー強迫性インベントリー):主に日常生活での強迫症の影響を評価する
- OCI-R(強迫性障害症状改訂版):強迫行為と強迫観念の両方を自己評価する
- HAM-A(ハミルトン不安定定量スケール):不安障害や強迫性障害の不安症状を定量的に評価する
強迫性障害の重症度を測る場合、代表的な評価方法として広く使われているのが、「Y-BOCS(イェール・ブラウン強迫スケール)」です。これは、強迫観念(頭に浮かぶ考え)と強迫行為(それを打ち消すための行動)について、それぞれ5項目ずつ、合計10項目を0〜4点の5段階で評価し、最大40点で重症度を測ります。
Y-BOCSの10つの評価項目
【強迫観念に関する5項目】
- 一日に強迫観念にとらわれている時間や頻度
- 強迫観念が社会生活や仕事へ与える支障の程度
- 強迫観念による苦痛の強さ
- 強迫観念に対する抵抗の程度
- 強迫観念の自己コントロールの程度
【強迫行為に関する5項目】
- 一日に強迫行為に費やす時間や頻度
- 強迫行為が社会生活や仕事へ与える支障の程度
- 強迫行為を妨げられたときの不安の程度
- 強迫行為に対する抵抗の程度
- 強迫行為の自己コントロールの程度
それぞれの合計点数によって、以下のように重症度を測ります。
| 合計点数 | 重症度 | 説明 |
| 0~7点 | – | 病気とはいえない |
| 8~15点 | 軽度 | 日常生活に大きな支障はない |
| 16~23点 | 中等度 | 少し不便さを感じる
自力で症状のコントロールが難しいと感じる 専門家に相談したいと思う人もいる |
| 24~31点 | 重度 | 日常生活や仕事に重大な支障があり、非常につらい
他者からの援助が必要 |
| 32~40点 | 極めて重度 | 生活の大半が症状に費やされる
生活が困難で引きこもり状態の人が多い 周囲の人の援助が多大 |
点数が高いほど、強迫症状が強い状態に近く、早期の治療が望まれます。
この方法を実施する際のポイントは、直近1週間の様子を思い出しながら回答すること、「強迫観念」と「強迫行為」の違いを理解した上で自己評価することです。
ただし、これらの尺度はあくまで症状の目安を知るためのものであり、自己診断だけで病気を確定することはできません。あくまでも結果を参考程度にとどめ、気になる症状がある場合は、必ず専門の心療内科や精神科を受診し、医師による診断とサポートを受けるようにしましょう。
※参考:日本不安症学会.「自己記入式 YALE-BROWN 強迫観念・強迫行為評価スケール(Y-BOCS)日本語版 」. https://jpsad.jp/files/JSARD_recommended_scale_Y-BOCS.pdf?1623318296 ,(2025-06-18).
強迫性障害の原因

強迫性障害の原因は完全には解明されていませんが、以下の要因が関与していると考えられています。
① 脳内の神経伝達物質の異常
セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質は、脳内で感情や行動のコントロールに重要な役割を果たしています。これらのバランスが崩れると、不安を抑える働きが低下し、強迫観念や強迫行為が増すと考えられています。特にセロトニンの不足は、強迫性障害の症状悪化と関連が深いとされており、薬物療法ではセロトニンの調整を目的とした治療が行われることが多いです。
② 遺伝的要因
強迫性障害は、家族内で発症する傾向があり、遺伝的要因が関与している可能性が指摘されています。親や兄弟に同様の症状を持つ人がいる場合、発症リスクが高まることが報告されていますが、環境やストレスなどの要因も影響を与えると考えられています。
③ 環境要因・ストレス
幼少期の厳格な教育や、強いプレッシャー、トラウマは、強迫性障害の発症リスクを高める要因とされています。過度な完璧主義の要求や、厳しいしつけにより不安が強まり、特定の行動を繰り返すことで安心を求める傾向が形成されることがあります。
強迫性障害が日常や家族に与える影響

強迫性障害は、本人の日常生活だけではなく、家族や周囲の人にも大きな影響を及ぼすことがあります。
家族や周囲を困らせてしまう
強迫性障害の症状によって、身近な家族や友人など、周囲の人を困らせてしまう場面が増えることがあります。 例えば、「火は消したか」「戸締まりをしたか」と家族に何度も確認を繰り返したり、アルコール消毒を強要したりなどです。周囲の人を巻き込むため、人間関係に支障が出やすくなります。
日常生活における行動が制限される
強迫観念や強迫行為が頻繁に起こることで、本人の行動が大きく制限されるようになります。身支度に極端な時間がかかって遅刻が増えたり、確認に時間がかかり過ぎて手続きなどが進められなかったりするため、スムーズに日常生活を送るのが困難です。社会への適応が難しくなるため、本人も大きなストレスを抱えてしまいます。
精神疾患の発症
強迫性障害が長期間続くと、うつ病や睡眠障害など、他の精神疾患を発症するリスクが高まります。症状への強いストレスや、社会生活に適応できない苦痛などが、二次的な精神疾患を引き起こす要因です。また、アルコールをはじめとした何らかの依存症になるケースもあります。
強迫性障害の治療法

強迫性障害には、症状の程度や状態に応じて複数の治療法があります。
① 薬物療法
強迫性障害の治療には、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が用いられることが一般的です。これにより、脳内のセロトニンバランスが整い、不安が軽減されることが期待されます。
② 認知行動療法(CBT)
認知行動療法(CBT)は、強迫性障害の治療で大きな効果があるとされ、不合理な考えや行動パターンを修正する方法です。「手を何度も洗わなければならない」という思考を「一度で十分」と認識し、不安に段階的に直面しながら強迫行為を控える訓練を行います。
③ 曝露反応妨害法(ERP)
認知行動療法(CBT)の一部として、曝露反応妨害法(ERP)があります。これは、不安を引き起こす状況にあえて直面し、強迫行為を行わずに過ごす訓練をする方法です。ただし、不安の少ない行為から徐々に取り組むことが重要で、医療者との信頼関係も大切です。症状が誘発され、パニック発作を引き起こすこともあるため、自己判断せず、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
強迫性障害は、適切な治療とサポートがあれば、症状をコントロールしながら生活することが可能な病気です。「なぜ自分はこんなに不安を感じるのか」「この行動をやめられないのはおかしいのか」と自分を責めず、まずは専門医に相談してみることが大切です。
決して一人で悩まず、家族や専門家の支援を受けながら、少しずつ不安とうまく付き合っていきましょう。
強迫性障害で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。強迫性障害は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」
「しっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
強迫性障害のご相談はLino clinicへ
メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、強迫性障害に対する診断・治療を行い、患者さま一人ひとりに合わせたサポートを提供しています。
・赤坂駅・天神駅から徒歩圏内で通いやすい
・土日祝も夜8時まで診療 →忙しい方でも通院しやすい
・当日予約可能 → お電話またはWEBでスムーズに予約
「この不安や行動が強迫性障害かもしれない…」「早く治療を始めて、日常生活を取り戻したい」と感じたら、ぜひLino clinicへご相談ください。あなたが安心して治療に向き合えるよう、スタッフ一同しっかりとサポートいたします。