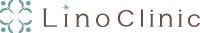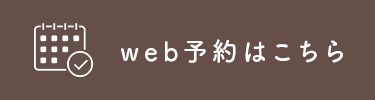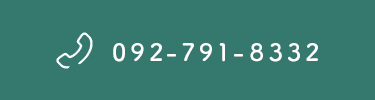睡眠障害(不眠症)とは?種類や原因、予防方法を解説

睡眠障害は、睡眠に関連する問題が日常生活や健康に影響を与える状態を指します。不眠症はその中でも一般的なタイプであり、寝つきが悪い、途中で目が覚める、または早朝に目が覚めて再び眠れないといった症状が特徴です。不眠症は一時的なものから慢性的なものまでさまざまであり、原因も多岐にわたります。
睡眠障害(不眠症)とは
私たちの健康や心の安定に欠かせない「睡眠」ですが、そのリズムが崩れると、心身にさまざまな影響を及ぼします。中でも代表的な睡眠障害が「不眠症」です。
3人に1人が睡眠の悩みを抱えている
日本では、約3人に1人が何らかの形で睡眠に関する悩みを抱えているといわれています。不眠症は、「夜寝つきが悪い」「途中で何度も目が覚める」「極端に朝早く目が覚めてしまう」「眠りが浅く熟睡できていない」といった症状が継続し、日中の生活に支障をきたす状態です。十分に寝られていないため、日中に眠気が続いたり集中力が低下したり、疲れやすかったりと、気分や体調に悪影響を及ぼします。単に眠れないだけではなく、生活の質を左右する深刻な問題として、適切な理解と対応が必要です。
不眠の悩みは加齢に伴い増加する
不眠に悩む人の割合は、加齢とともに増加する傾向があります。年齢を重ねると必要な睡眠時間が短くなり、睡眠と覚醒のメリハリが緩やかになっていきます。特に60歳を過ぎる頃からは、基礎代謝が低下し、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が減少するため、眠りが浅くなりがちです。
さらに、日中の活動量が減ることで夜に眠気が起こりにくくなり、昼間の眠気を補おうとすることで、かえって寝つきが悪くなるという悪循環に陥ることもあります。眠れないことへの不安や焦りがさらなる不眠を招くこともあるので、必要以上に睡眠時間の確保にこだわり過ぎないことも大切です。
また、加齢とともに高血圧や糖尿病などの持病の数が増えると、睡眠の質の低下につながることも指摘されています。
睡眠障害の種類

睡眠障害には多くの種類があり、それぞれの特徴や原因が異なります。以下で主な睡眠障害の種類、症状の特徴、原因を詳しく解説します。
不眠症
不眠症には以下のような特徴があります。
- 主な症状:寝つきの悪さ、夜間の覚醒、早朝の覚醒、睡眠の質の低下
- 原因:ストレス、生活習慣の乱れ、身体的または精神的な疾患
- 影響:疲労感、集中力低下、日中の眠気
寝つきの悪さ
入眠障害は、布団に入っても30分~1時間以上かかり、寝つくことができず苦痛に感じます。考えごとが止まらなかったり、不安や緊張感が強いときに起こりやすく、ストレスや生活習慣の乱れが影響していることもあります。不眠のタイプの中で比較的多い悩みです。
夜間の覚醒
中途覚醒は、夜中に何度も目が覚めてしまう状態で、一度目が覚めると再び眠るのが難しくなります。断続的な睡眠により、疲れが取れにくくストレスになることも多いです。中高年に多く見られます。
早朝の覚醒
早朝覚醒は、起床予定時刻より2時間以上早く目が覚め、その後再び眠れない状態です。高齢者に多く見られますが、うつ病などの精神的な要因が隠れていることもあります。睡眠を誘導するホルモン「メラトニン」の不足が考えられます。
睡眠の質の低下
熟眠障害は、十分な時間睡眠を取っていても、熟睡したという満足感が得られず、睡眠不足を感じる状態です。朝スッキリと起きられず、日中に倦怠感や眠気が出るため、注意力や集中力の低下につながります。睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害(寝ている間に足がぴくんぴくんと繰り返し動く)などの病気との関係が疑われることもあります。
睡眠時無呼吸症候群
- 主な症状:睡眠中の呼吸停止、いびき、日中の過剰な眠気
- 原因:気道の閉塞や狭窄、肥満、加齢
- 影響:高血圧、心疾患、脳卒中のリスク増加
過眠症
- 主な症状:過剰な眠気、長時間の睡眠にもかかわらず疲労感が残る
- 原因:神経系の異常、薬物の副作用、睡眠の質の低下
- 影響:日常生活や仕事のパフォーマンス低下
ナルコレプシー
- 主な症状:日中に突然強い眠気が襲う、睡眠麻痺、入眠時幻覚
- 原因:脳内の神経伝達物質の異常
- 影響:運転や作業中の危険
概日リズム睡眠障害
- 主な症状:体内時計が昼夜の環境とずれることで起きる不眠や過眠
- 種類:遅発性睡眠相症候群、シフトワーク睡眠障害、非24時間睡眠覚醒症候群
- 原因:不規則な生活、夜勤、時差ぼけ
- 影響:慢性的な疲労、集中力の低下
むずむず脚症候群(RLS)
- 主な症状:就寝中やリラックス時に脚がむずむずする不快感、動かすことで軽減
- 原因:遺伝的要因、鉄欠乏、神経疾患
- 影響:入眠困難、睡眠の質の低下
睡眠時行動異常症(REM睡眠行動障害)
- 主な症状:夢に連動して体を動かす、暴れる、叫ぶ
- 原因:神経変性疾患(パーキンソン病など)、特定の薬剤の副作用
- 影響:自己または同伴者へのけが、睡眠の中断
これらの睡眠障害は、それぞれ特有の治療法や対処法が必要です。適切な診断と治療を受けることが重要です。
※出典:厚生労働省.「休養・こころの健康 / 睡眠障害」.https://kennet.mhlw.go.jp/home ,(参照2025-06-16).
不眠症の症状と影響

先述のように、睡眠障害の中でも、不眠症の症状には以下のものが含まれます。
- 寝つきが悪い(入眠障害)
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 朝早く目覚め過ぎる(早朝覚醒)
- 十分に睡眠をとっても疲労感が残る(熟眠障害)
これらの症状が続くと、以下のような影響が出ることがあります。
- 集中力の低下
- 情緒不安定
- 免疫力の低下
- 生活の質の低下
不眠症の原因

不眠症には多くの原因があり、それぞれ異なる対処法が必要です。
心理的要因
ストレスやうつ病、不安障害は不眠症の主な心理的要因です。ストレスが続くと脳が興奮状態になり、寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めたりしやすくなります。うつ病や不安障害では、ネガティブな思考が睡眠を妨げることが多く、慢性的な不眠につながることがあります。
身体的要因
慢性疾患や慢性的な痛み、ホルモンバランスの乱れも、不眠症の原因となることがあります。持続する痛みは眠りを妨げ、睡眠の質を低下させます。またホルモンの変動により、自律神経が乱れやすくなり、寝つきが悪くなったり途中で目が覚めたりすることもあるでしょう。
環境的要因
騒音や光、寝具の不適合も、不眠症の原因です。外の騒音や強い光は眠りを妨げ、睡眠の質を低下させます。また硬過ぎる・柔らか過ぎる寝具や合わない枕は体の負担となり、寝つきの悪さや途中で目が覚める原因になることがあります。
生活習慣
不規則な生活やカフェイン・アルコールの過剰摂取も、不眠の原因です。就寝時間が一定でないと体内リズムが乱れ、眠りが浅くなります。カフェインは覚醒作用があり、就寝前の摂取で寝つきが悪くなることがあります。アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠の質を低下させ、途中で目が覚めやすくなります。
睡眠障害の診断

睡眠障害は自覚しにくいケースも多く、放置すると心身に深刻な影響を及ぼします。まずは自分の睡眠の状態を把握することが大切です。以下のセルフチェック項目を参考に、日常生活に支障が出ていないかを確認してみましょう。
- 布団に入っても30分~1時間以上眠れないことが頻繁にある
- 夜中に何度も目が覚めて熟睡感がない
- 起床予定時刻よりもかなり早く目が覚め、再び眠れない
- 睡眠時間は足りているのに、満足感がない
- 寝ても疲れが取れないと感じる
- 日中に強い眠気があり、居眠りをしてしまう
- 日中に気分が滅入る、活動量が低下する
- 集中力が続かず、仕事や日常生活に支障が出ている
- 寝る前に足がむずむずして、動かさずにはいられない
- 睡眠中に大きないびきをかいたり、呼吸が止まったりする
- 睡眠中に大きな寝言や叫んだり、寝ぼけて行動したりする
- 睡眠中に足がぴくんぴくんと繰り返し動く
上記にあてはまる項目がいくつかあり、その状態が長期間続く場合は、単なる寝不足ではなく、睡眠障害の可能性があります。自己判断に頼らず、早めに医療機関に相談することが改善の第一歩です。
睡眠障害(不眠症)の自己対策と予防方法

不眠症の軽減には、以下の自己対策が役立つことがあります。実践できそうなものから日常生活に取り入れてみましょう。
睡眠習慣を整える
毎日同じ時間に寝て起きることは、体内リズムを整え、不眠症の改善に役立ちます。就寝・起床時間を一定にすることで、自然な眠気が訪れやすくなり、睡眠の質が向上するでしょう。特に休日もリズムを崩さずに過ごすことが重要で、寝過ぎや昼寝のし過ぎを避けることで、夜の寝つきを良くする効果が期待できます。
適切な環境を作る
静かで暗い環境を整えることは、質の良い睡眠に欠かせません。寝室の光や騒音を遮る工夫をし、リラックスできる空間を作ることが大切です。また室温が高過ぎたり低過ぎたりすると眠りが浅くなるため、快適な温度(約18~22℃)と適度な湿度を保つことで、深い睡眠をサポートできます。
リラクゼーション法
深呼吸や瞑想、ヨガは、不眠症の改善に役立つリラクゼーション法です。深呼吸は副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせます。瞑想は頭の中を整理し、不安やストレスを和らげる効果が期待できます。ヨガは筋肉の緊張をほぐし、血流を促進することで、自然な眠気を誘える取り組みです。就寝前に取り入れることで、より質の高い睡眠が期待できます。
刺激物を控える
カフェインやアルコールの摂取を控えることは、良質な睡眠を確保するために重要です。上記で説明したように、カフェインには覚醒作用があり、就寝前に摂ると寝つきが悪くなり、眠りが浅くなることがあります。アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠の質を低下させ、途中で目が覚めやすくなります。午後以降はカフェインを控え、アルコールの過剰摂取を避けることで、安定した睡眠を得やすくなるでしょう。
クリニックでの治療

不眠症が慢性化している場合は、専門的な治療が必要です。クリニックでは、以下のようなアプローチが取られることがあります。
認知行動療法(CBT-I)
不眠症に特化した心理療法として、認知行動療法(CBT-I)が有効とされています。不眠の原因となる思考や行動のパターンを見直し、適切な睡眠習慣を身に付けることを目的とした治療法です。具体的には、睡眠日誌の記録やリラクゼーション法の実践、ベッドでの過ごし方の改善などを行い、睡眠の質を向上させることを目指します。
薬物療法
不眠症の治療では、短期的に睡眠導入剤や抗不安薬が処方されることがあります。これらの薬は寝つきを良くしたり、不安を和らげたりする効果がありますが、長期使用は依存や耐性のリスクがあるため、医師の指導の下適切に使用することが大切です。
生活指導
不眠症の改善には、生活習慣の見直しやストレスマネジメントが重要です。規則正しい睡眠リズムを保ち、適度な運動やリラックスできる時間を確保することで、睡眠の質が向上します。またストレスをため込まないよう、深呼吸や瞑想などのリラクゼーション法を取り入れることも効果的です。
まとめ
睡眠障害(不眠症)は、心身に大きな負担を与えるため、早期に適切な対処が必要です。生活習慣の見直しやリラックス法を取り入れること、そして専門的なサポートを受けることが改善への第一歩です。睡眠の質を向上させることで、日中の疲労感やストレスが軽減され、心と体の健康が保たれます。
不眠症で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。不眠症は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」
「不眠症をしっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
Lino clinicでは
メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、不眠症を含むさまざまな睡眠障害に対して、専門的な治療を提供しています。当院の特長は以下の通りです。
- アクセスの良さ:赤坂駅や天神駅から徒歩圏内にあり、通いやすい環境です。
- 柔軟な診療時間:平日だけでなく、土日祝日も20時まで診療しています。
- 専門的なサポート:不眠症の原因に合わせた治療計画を立て、患者様一人ひとりに寄り添った対応を行います。
不眠症に悩んでいる方は、一度Lino clinicにご相談ください。当日予約も可能で、電話またはWEBからお申し込みいただけます。