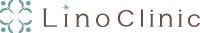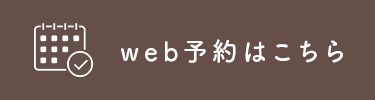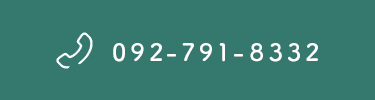統合失調症とは?原因や主な症状、治療法を解説
統合失調症は、思考や感情、行動に影響を与える精神疾患の一つです。幻覚や妄想、思考の混乱といった症状が特徴で、現実との区別が難しくなることがあります。これらの症状により、日常生活や社会生活に大きな影響を及ぼすこともあるでしょう。しかし、適切な治療を受けることで、症状をコントロールし、安定した生活を送れるようになります。
もし、「最近、現実感がなくなっている気がする……」「周囲が自分を監視しているように感じる……」などの違和感をおぼえているなら、一人で悩まずに専門家に相談してみてください。統合失調症は決して珍しい病気ではなく、適切な治療で回復が期待できる病気です。
本記事では、統合失調症の特徴や症状、原因、治療法について詳しく解説していきます。
統合失調症とは?
統合失調症とは、思考や感情、行動に著しい影響を及ぼす精神疾患です。主な症状には、幻覚や幻聴、妄想、認知機能の低下、感情の平板化などが挙げられます。
統合失調症の原因は、まだ明確には解明されていませんが、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることや、脳の働きに異常が生じることが原因と考えられています。
遺伝的な要因が関与しているといわれていますが、それだけではなく、環境要因によって大きなストレスがかかることも関係しているようです。さまざまな要因が複雑に影響し合うことで発症するとされています。
この病気は、10代から20代にかけて発症することが多く、男女ともに見られます。発症後、適切な治療を受けずに放置すると、症状が悪化し、社会生活や人間関係に大きな支障をきたすことがあるため、早期発見と早期治療が非常に重要です。
統合失調症の経過

統合失調症は、症状の現れ方に個人差があるものの、一般的には「前兆期」「急性期」「回復期」「安定期・慢性期」という4つの経過をたどることが多いとされています。それぞれの時期には特徴的な症状や注意すべきポイントがあり、適切な対応が必要です。進行の仕方や回復のスピードには幅があり、症状の程度や周囲の支援環境によっても大きく異なります。本人だけではなく家族や支援者も、経過をよく理解しておきましょう。
前兆期
統合失調症の前兆期では、幻覚や妄想といったはっきりした症状が現れる前に、心身にさまざまな違和感が出てきます。不眠や漠然とした不安感、神経過敏、気分の浮き沈み、集中力の低下、イライラなどがよく見られます。
周囲から見ると、これまでと違う反応を示したり、学校や仕事を休みがちになったりするなどの行動変化が見られることも特徴です。本人自身が「なんとなく調子がおかしい」と感じることもありますが、自覚しづらいケースも少なくありません。目立った症状ではないため周囲も見過ごしやすく、早期発見が難しい段階ですが、過労やストレス、睡眠不足を避け、変化に気づいたら早めの受診や相談が重要です。
急性期
前兆期の後にあたる急性期では、統合失調症の症状が本格的に現れます。この時期は「陽性症状」と「陰性症状」が強いのが特徴です。
陽性症状とは、幻覚(特に幻聴)や妄想、興奮、思考の混乱、昏迷などがあり、現実との区別がつかなくなるため、本人は非常に混乱しやすくなります。また、周囲との会話が成り立たなくなるなど、社会的な関わりが困難になることもあります。
一方、陰性症状としては、意欲の低下や感情表現の乏しさ、無気力、引きこもりなどが主な傾向です。本人は「何かがおかしい」と感じながらも、自分が病気だと認識できないことが多く、治療への抵抗感を示す場合もあります。急性期は特に周囲の理解と支援が不可欠な時期です。
回復期
回復期では、陽性症状である幻覚や妄想が徐々に落ち着き、症状が軽減していく時期です。ただし、陰性症状がしばらく残ることが多く、無気力や抑うつ、引きこもりなどが続くケースもあります。また、この時期には注意力や記憶力、判断力などの認知機能の低下が目立つことがあり、社会生活への復帰を難しくする要因となる場合もあります。
回復には数ヵ月から数年単位の時間を要することがあり、焦らず段階的に生活リズムを整えていくことが大切です。また、症状が落ち着いていても、強いストレスや環境の変化などによって再発するリスクもあります。服薬の継続や定期的な通院が再発予防につながります。
安定期・慢性期
安定期・慢性期は、急性期のような強い症状が落ち着き、症状がある程度固定化してくる段階です。多くの方が、日常生活を一定のリズムで過ごせるようになりますが、陰性症状や認知機能の低下が長く続くこともあり、社会参加や人間関係において困難を抱えることもあります。感情表現が乏しくなったり、物事への関心が薄れるなど、周囲からは「元気がない」「やる気がない」と誤解されやすい状態になることもあります。
この時期は、無理なく生活の幅を広げていくことが大切です。本人のペースに合わせて、復職や復学、社会復帰の支援を行いましょう。また、症状が安定していても服薬を自己判断で中断せず、治療を継続することが再発防止に有効です。
統合失調症の主な症状

統合失調症の症状は、大きく以下の3つに分類されます。
① 陽性症状(現実には存在しないものを感じる)
- 幻覚(特に幻聴)
実際には存在しない声や音が聞こえる状態です。「誰かに悪口を言われている」「命令されている」などの内容が多く、強い不安や混乱を引き起こします。幻聴が続くと、現実と幻想の区別が難しくなることがあります。
- 妄想(被害妄想など)
「誰かに監視されている」「常に見張られている」と強く思い込む状態です。根拠のない疑念が膨らみ、周囲への警戒心が高まり、人間関係や日常生活に支障を来すことがあります。場合によっては恐怖心から攻撃的な行動を取ることもあります。
- 思考の混乱
話の内容がまとまらず、一貫性がなくなる状態です。話が飛びやすく、途中で脱線したり、他人には理解しにくい言葉のつながりになったりすることがあります。思考が混乱すると、会話のキャッチボールが難しくなり、社会生活に影響を与えることがあります。
② 陰性症状(感情や意欲の低下)
- 感情表現の減少
統合失調症の症状の一つで、喜怒哀楽が乏しくなり、表情や声の抑揚が少なくなる状態です。周囲から「冷たい」「無関心」と誤解されることもありますが、本人の意思とは関係なく、感情を表に出すことが難しくなることがあります。
- 意欲の低下
統合失調症の陰性症状の一つで、身の回りのことへの関心がなくなり、仕事や学業、日常の活動に対する意欲が低下する状態です。食事や入浴などの基本的な生活習慣が乱れやすくなり、社会生活への適応が困難になることがあります。
- 社会的引きこもり
統合失調症の陰性症状の一つで、人との関わりを避け、長期間家に閉じこもる状態を指します。人と話すことが苦痛になり、家族との会話も減少することがあります。孤立が進むと、社会復帰が難しくなるため、早めの治療や支援が重要です。
③ 認知機能の障害(考える力の低下)
- 注意力の低下
統合失調症の認知機能障害の一つで、集中力が続かなくなる状態です。本を読んでも内容が頭に入らなかったり、会話の途中で話が理解できなくなったりすることがあります。仕事や学業に支障をきたし、日常生活にも影響を及ぼします。
- 記憶力の低下
統合失調症の症状の一つで、新しいことを覚えにくくなったり、以前の出来事を思い出しにくくなったりする状態です。仕事や学習の効率が下がり、会話の内容を忘れてしまうこともあります。これにより、人間関係にも影響を及ぼすことがあります。
- 判断力の低下
統合失調症の認知機能障害の一つで、適切な選択ができなくなる状態です。簡単な決断に時間がかかったり、場面に合わない行動を取ってしまったりすることがあります。これにより、日常生活や社会生活に困難を感じることが増えることがあります。
統合失調症の受診をした方が良い前兆

統合失調症の前兆期の症状が見られた場合は、早期の受診がおすすめです。統合失調症と診断されにくいことも多いですが、症状が現れた時点で受診することで、高い治療効果が期待できます。
神経過敏
統合失調症の前兆期に見られる症状の一つが「神経過敏」です。光や音、匂い、人の視線などに対して、過剰に敏感になる状態を指します。例えば、わずかな物音に驚いたり、テレビの音声や画像が強く不快に感じられたり、人混みの中で他人の視線が気になって外出がつらくなることもあります。
また、周囲の些細な出来事に過剰に意味を見出してしまうこともあり、本人にとっては強いストレスとなります。こうした状態が長く続いたり、日常生活に影響を及ぼすようであれば、早めに専門機関を受診することが大切です。
強い不安や緊張など
統合失調症の前兆として、理由のない強い不安や緊張が続くことがあります。例えば、「周囲の視線が気になる」「誰かに監視されている気がする」といった被害的な感覚に悩まされたり、日常の出来事に対して過敏に反応してしまうことがあります。
また、焦燥感やイライラ、不眠、食欲不振といった身体的な症状を伴うことも少なくありません。これらの状態が長引くと、学校や仕事、人間関係にも支障が出てくることがあります。心身のバランスが崩れていると感じたら、早期に専門医へ相談することが重要です。
統合失調症の原因

統合失調症の正確な原因は解明されていませんが、以下のような要因が関与していると考えられています。
① 脳内の神経伝達物質の異常
統合失調症の発症に関与すると考えられているのが、ドーパミンやグルタミン酸といった神経伝達物質の異常です。特に、ドーパミンが過剰に分泌されると、脳の情報処理がうまく機能せず、幻覚や妄想が引き起こされる可能性があります。
またグルタミン酸の働きが低下すると、思考のまとまりがなくなり、注意力や判断力の低下につながることがあります。これらの神経伝達物質のバランスが崩れることが、統合失調症の症状が現れやすくなる原因の一つです。
② 遺伝的要因
家族に統合失調症の人がいる場合、発症リスクが高まることが指摘されています。ただし、遺伝だけで発症するわけではなく、環境要因も影響を与えると考えられています。
③ 環境的要因・ストレス
過度なストレスや家庭環境の問題、人間関係のトラブル、生活環境の変化なども、発症の引き金となり得る要因です。特に、思春期や若年成人期に強いストレスを受けることが、発症リスクを高めるとされています。
統合失調症の治療法

統合失調症は、適切な治療を受けることで症状をコントロールし、社会生活を維持することが可能です。主な治療法には、薬物療法や心理療法、生活習慣の改善、精神科のリハビリテーションが挙げられます。
① 薬物療法(抗精神病薬)
統合失調症の治療の基本は、抗精神病薬を服用することです。これにより、幻覚や妄想などの症状が抑えられます。
- 定型抗精神病薬
以前から使用される統合失調症治療薬で、幻覚や妄想などの陽性症状に効果が期待できる。ドーパミンの過剰な働きを抑え症状を改善するが、錐体外路症状(筋こわばり・震え)などの副作用が現れることがある。
- 非定型抗精神病薬
比較的新しい統合失調症治療薬で、陽性症状だけではなく陰性症状に対しても使われることがある。ドーパミンとセロトニンの調整作用があり、副作用が少ないが、体重増加や代謝異常に注意が必要。
これらの抗精神病薬の他に、症状に合わせて以下のような薬が処方されることもあります。
- 症状を調整する薬
統合失調症の主な症状である、強い不安感や緊張感の緩和には「抗不安薬」、激しい気分の落ち込みや意欲低下などの抑うつ症状には「抗うつ薬」が挙げられる。また、眠りが浅い、寝付きが悪い、早朝に目が覚めるなどの不眠症状や昼夜逆転の症状には、「睡眠薬」で睡眠リズムを調整する。
- 抗精神病薬の副作用を抑える薬
抗精神病薬による副作用が強い場合、症状を抑える薬を併用することがある。手の震えや身体のこわばり、足がむずむずする感覚などの錐体外路症状には「抗パーキンソン病薬」が一般的。便秘症状には「便秘薬」で便通を良くする。
副作用症状
抗精神病薬を服用することによる副作用の現れ方には、個人差があります。副作用の例は、体がこわばり硬くなったように感じたり、手足がふるえたりするケースです。中には落ち着きがなくなる方もいます。また、のどの渇きや便秘の症状が現れるケースもあります。少しでもこのような変化を感じたら、主治医に相談すると良いでしょう。薬の種類や組み合わせを変える、服用の量を調整するなどの対応を取ってもらえます。
② 認知行動療法(CBT)
統合失調症の治療の一環として、幻覚や妄想への対処法を学び、不安を軽減するために行われる治療法です。患者が自分自身の考え方を客観的に見直し、非現実的な思考を修正することで、現実的な視点を持てるよう支援します。例えば、「誰かに監視されている」という妄想に対して、その根拠を冷静に検証し、不安を軽減する練習を行うなどです。
また幻覚による影響をできるだけ抑え、日々の暮らしをより良くするためには、ストレス管理やリラクゼーション法を学ぶことも有効です。
③ 生活習慣の改善
- 規則正しい生活を送る(食事・睡眠・運動のリズムを整える)
- ストレスを避ける(リラックスできる環境をつくる)
- 家族や支援者との関係を大切にする(孤立を防ぐ)
④ 精神科リハビリテーション
精神科リハビリテーションは、病気の症状によって生活しにくい部分を改善に向かわせ、スムーズで安定した生活を送れるようにすることを目指す取り組みです。
- デイケアサービス
医療機関、保健所、精神保健福祉センターなどで実施されている外来治療の一つ。心理教育、レクリエーション、軽作業などを通じて対人関係能力を身に付ける。
- 作業療法
軽作業(手工芸、体操、園芸、音楽など)を通じて楽しみや達成感などの感情を回復させ、日常生活や社会参加へつなげる。
- SST(社会生活技能訓練)
対人関係スキル、病気や薬への向き合い方、ストレス対処法などをロールプレイング形式を取り入れて学び、自信の回復を図り、再発防止や社会生活安定を目指すとするトレーニング
- 心理教育
病気や治療法などについて正しく学び、前向きに治療に取り組めるようにする。家族を対象とした心理教育もある。
まとめ
統合失調症は、適切な治療と生活の調整が大切な疾患です。自分に合ったペースで治療や生活改善を進めることで、症状をコントロールし、社会生活を送ることも可能になります。「自分の症状が統合失調症かもしれない……」「最近、周囲のことが気になり過ぎて生活がつらい……」と感じたら、早めに専門医に相談することをおすすめします。
決して一人で抱え込まず、医療機関や家族、周囲のサポートを受けながら、焦らず治療に向き合っていきましょう。
統合失調症で休職を考えている方へ
毎日頑張りすぎていませんか?環境の変化や職場のストレスで心身が限界を感じているなら、無理をせず一度立ち止まることも大切です。統合失調症は、無理を続けることで悪化し、長期の不調につながることもあります。
「心身ともに限界で、早急に休職したい…。」
「しっかり治して、また職場に戻りたい…。」
そんな思いを抱えている方が、安心して治療に専念できるよう、メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、休職や復職のために必要な診断書を、最短即日で発行できる体制を整えております。少しでも早く、心と体を休められるよう、お気軽にご相談ください。※症状や診断の内容によっては、当日に診断書を発行できない場合があります。適切な診断を行うために、詳細な問診や追加の評価が必要になることがあるためです。あらかじめご了承ください。
統合失調症のご相談はLino clinicへ

メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、統合失調症の診断・治療を行い、患者さま一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。
統合失調症は、一人で抱え込まずに専門医と一緒に向き合うことで、症状のコントロールが可能な病気です。
Lino clinicでは、アクセスしやすい立地で、土日祝日も20時まで診療しており、忙しい方でも無理なく通院できます。また、当日予約も可能なので、「今すぐ相談したい」という方にも対応可能です。
あなたの不安や悩みに寄り添いながら、最適な治療を提供いたします。少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。あなたが穏やかな日常を取り戻せるよう、私たちがしっかりとサポートいたします。