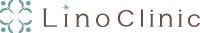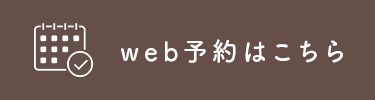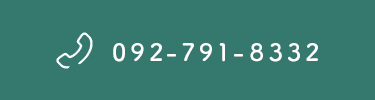PMS(月経前症候群)とは?
PMS(月経前症候群)とは、生理前の3〜10日間に起こる身体的・精神的な不調のことを指します。
多くの女性が経験し、症状の種類や程度は個人差が大きいですが、日常生活に支障をきたすこともあります。
PMSは、ホルモンバランスの変化によって引き起こされるとされており、適切な対処をすることで症状を軽減できます。
本記事では、PMSの原因や症状、診断方法、治療法、そして日常生活での改善策について詳しく解説します。
PMS(月経前症候群)の主な症状

PMS(月経前症候群)では、生理が始まる3〜10日前から、さまざまな身体的・精神的な不調が現れます。
症状の出方や程度は人によって大きく異なり、軽い違和感で済む人もいれば、日常生活に支障が出るほどつらい症状を抱える人もいます。
ここでは、PMSの代表的な症状を「身体的症状」と「精神的症状」に分けて詳しく紹介します。
身体的症状
PMSによる身体の変化は、ホルモンバランスや水分代謝の変化、消化機能の影響などにより引き起こされます。
- 頭痛
特にこめかみがズキズキするような片頭痛タイプが多く、痛み止めが効きにくい場合もあります。 - 乳房の張りや痛み
プロゲステロンの影響により、胸が張って重く感じたり、触ると痛みを感じたりすることがあります。 - 腹部の膨満感
お腹が張って苦しい、ズボンがきつく感じるといった感覚です。 - むくみ(特に手足や顔)
水分が体内にたまりやすくなり、指輪がきつくなる・靴がきつく感じる・顔が腫れぼったいなどの症状が出ます。 - 便秘や下痢
ホルモンの影響で、腸の動きが乱れるため、便秘・下痢のどちらか、または交互に現れることもあります。 - 疲労感
ぐったりとだるく、十分な睡眠をとっても疲れが抜けないと感じる人もいます。 - 眠気や不眠
日中強い眠気を感じる一方で、夜に眠れなくなることもあり、生活リズムが乱れやすくなります。 - 体重増加(体内の水分量の変化による)
食欲が増すこともありますが、多くはホルモン変化による水分の貯留によって一時的に体重が増えるのが原因です。
精神的症状
PMSは心の面にも強く影響を及ぼします。普段は気にならないことが気になったり、感情のコントロールが難しくなるのが特徴です。
- イライラしやすい
些細なことで怒りっぽくなり、自分でも感情のコントロールが難しくなることがあります。 - 抑うつ感や気分の落ち込み
気分が重く、無気力になったり、何もしたくない状態に陥ることもあります。 - 集中力の低下
本を読んでも内容が入ってこない、仕事や勉強に身が入らないといった状態が続きます。 - 不安感が強くなる
普段は気にしないようなことでも、過度に不安を感じてしまうことがあります。 - 泣きたくなる
感情が不安定になり、ちょっとしたことで涙が出そうになることがあります。 - 怒りっぽくなる
感情の起伏が激しくなり、イライラと怒りが続くことがあります。 - 社交的でなくなる
人と会うのが億劫になり、外出や会話を避けたくなる傾向が見られます。
症状は「生理が始まると改善する」のが特徴
PMSの症状は、多くの場合、生理が始まると自然に軽減・消失します。
しかし、症状が重くなると、仕事・学業・家庭生活・人間関係に深刻な影響を与えることもあります。
- 「自分だけがこんなに苦しいのかも」と思いがちですが、PMSに悩む女性は少なくありません。
- つらい場合は、我慢せずに婦人科や心療内科などの専門医に相談することが大切です。
PMS(月経前症候群)の原因

PMS(月経前症候群)は、多くの女性にとって身近な不調ですが、その原因はひとつではありません。
現在のところ完全には解明されていないものの、以下の3つの要因が密接に関係していると考えられています。
1. ホルモンバランスの変化
生理周期の後半、排卵後から生理開始までの期間(黄体期)には、2つの女性ホルモンが大きく変動します。
- エストロゲン(卵胞ホルモン)
- プロゲステロン(黄体ホルモン)
このホルモンバランスの変化が、脳に影響を与える神経伝達物質の分泌に影響し、気分の不安定さや身体の不調が起こると考えられています。
特に、プロゲステロンが増える時期には、体温が上がりやすく、むくみや眠気が出るほか、情緒も不安定になりやすいとされています。
2. 神経伝達物質の変化
脳内のセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質も、PMSの症状に大きく関与しています。
- セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させる働きを持っています。
生理前にはこのセロトニンの分泌が低下しやすく、イライラ、不安感、抑うつ感、眠気などの精神的な不調が現れやすくなります。 - ドーパミンの減少も、やる気や集中力の低下につながると考えられています。
つまり、ホルモンの影響を受けて、脳の「感情をコントロールする仕組み」が一時的に不安定になるというわけです。
3. 生活習慣やストレス|日々の積み重ねが症状を左右する
PMSの症状を悪化させる“外的要因”として注目されているのが、生活習慣とストレスです。
悪化しやすい生活習慣の例:
- 睡眠不足や不規則な生活リズム
体内時計の乱れがホルモン分泌にも影響を与えます。 - 過度なストレスや心の緊張状態
ストレスホルモンが増えることで、気分の波が激しくなることがあります。 - 栄養の偏り・カフェイン・アルコール・糖分の過剰摂取
これらは一時的な気分の高揚感をもたらすものの、その後に急激な不調を引き起こす原因になることもあります。
つまり、ホルモンバランスの変化に加えて、生活習慣の乱れが症状を強めることがあるという点にも注目が必要です。
PMSは「多要因」で起こる体と心の変化
PMSの原因は「ホルモンのせい」と一言で済ませられない、心と体が密接に関わる複雑な現象です。
- ホルモンと神経伝達物質の連携
- 日々の生活習慣やストレスの影響
- 女性の体が持つ自然なリズム
これらが重なったときに、PMSの症状として心身に現れてくると考えると、症状を「自分の弱さ」と捉える必要はまったくありません。
きちんと理解し、丁寧に向き合うことが、症状の軽減と快適な毎日に繋がります。
(出典:公益社団法人日本産婦人科学会 月経前症候群(premenstrual syndrome : PMS))
PMS(月経前症候群)の診断方法

PMS(月経前症候群)は多くの女性が抱える不調ですが、その診断には問診や記録などの客観的な確認が重要になります。
医療機関では、「どのような症状が、いつ、どのように出ているか」を明らかにしながら、PMSか、それとも別の疾患かを慎重に判断していきます。
1. 問診
診察では、まず医師が現在の症状やこれまでの経過について詳しく聞き取り(問診)を行います。
具体的に問われる内容:
- どのような症状があるか(身体的・精神的)
- それが生理のどれくらい前に始まり、いつ終わるか
- 生活にどの程度支障があるか(仕事・家事・人間関係など)
- 過去の婦人科疾患や精神的な既往歴
PMSの診断には、日常生活への影響を医師が具体的に把握することが大切です。
2. 月経カレンダーの記録
PMSの診断で特に重視されるのが、症状の出現時期と生理との関係です。
そのために医師から勧められるのが、月経カレンダー(症状日記)の記録です。
推奨される記録期間:
- 最低でも2〜3か月間、毎日以下のような内容を記録します。
記録する項目の例:
- 生理の開始日と終了日
- 身体症状(頭痛、腹痛、むくみなど)
- 精神症状(イライラ、落ち込み、涙もろさなど)
- 睡眠や食欲の状態
- 生活にどれだけ影響が出ているか(仕事に行けたか、気分はどうか など)
この記録によって、症状が「生理前に毎回現れて、生理が始まると軽快する」パターンがあるかが確認されます。
※ PMSは「日常のストレス」や「慢性的な不調」と見分けがつきにくいため、記録の積み重ねが正確な診断への第一歩です。
3. PMDD(月経前不快気分障害)との鑑別
PMSの中でも、特に精神的な症状が強く、生活に重大な支障をきたすものは、PMDD(月経前不快気分障害:Premenstrual Dysphoric Disorder)と診断されることがあります。
PMDDの特徴:
- うつ病に似た強い抑うつ感や絶望感がある
- 怒りやイライラが爆発的になる
- 人間関係が破綻するほど感情の起伏が激しい
- 自傷行為や自殺念慮に至るケースも
PMSとPMDDは症状の種類が似ていても、重症度が大きく異なるため、精神科や心療内科での専門的な診断が必要です。
自分の状態を「知る」ことが治療の第一歩
PMSの診断には、特別な検査機器や血液検査よりも、「日々の自分の記録」が大切です。
「気のせいかな?」「我慢しなきゃ」と思っていても、記録を見返すことで初めて“パターン化された不調”だと気づけることがあります。
- 少しでも「毎月同じ時期につらくなる」と感じる方は、まず症状日記をつけてみることをおすすめします。
- その記録をもとに、婦人科や心療内科で相談することで、適切な対処法が見つかります。
PMS(月経前症候群)の治療法

PMS(月経前症候群)の症状は、軽いものから日常生活に支障をきたすものまでさまざまです。
そのため、治療法も「体質や症状の程度に応じた個別対応」が基本となります。
治療は大きく分けて、薬物療法(医療的アプローチ)と非薬物療法(生活習慣の改善)の2つがあります。
ここでは、それぞれの治療法について詳しく解説していきます。
1. 薬物療法
● 低用量ピル(経口避妊薬)
- 女性ホルモンの変動を安定させる効果があり、PMSの根本的な症状改善が期待できます。
- 排卵を抑えることでホルモンの急激な変化を防ぎ、イライラや頭痛、むくみなどを軽減できます。
● 抗うつ薬(SSRI)
- セロトニンの働きを助け、気分の変動・抑うつ感・不安感を軽減します。
- 代表的な薬剤にはフルオキセチン(プロザック)やエスシタロプラム(レクサプロ)などがあります。
● 鎮痛剤(NSAIDsなど)
- 頭痛・腹痛・腰痛など、身体の痛みを和らげるために使用されます。
- 市販薬で対応可能な場合もありますが、強い痛みには処方薬が用いられます。
● 利尿剤
- 手足や顔のむくみが強い場合に処方されることがある薬です。
- 体内の余分な水分を排出することで、不快感を軽減します。
※ 薬物療法は症状に合わせて医師が慎重に処方するものであり、自己判断での服薬は避けましょう。
2. 非薬物療法
● バランスの取れた食事
食事の見直しは、ホルモンや神経伝達物質のバランスを整えるうえでとても重要です。
特に効果的なのが、ビタミンB6とマグネシウムを多く含む食品の摂取です。
◎ ビタミンB6を多く含む食品
- 肉類:鶏ささみ、牛レバー、豚ヒレ肉
- 魚類:マグロ、サーモン、イワシ
- 野菜・果物:バナナ、にんにく、アボカド
- 豆類:大豆、ひよこ豆、レンズ豆
◎ マグネシウムを多く含む食品
- ナッツ類:アーモンド、カシューナッツ、ピーナッツ
- 海藻類:わかめ、ひじき、のり
- 種子類:かぼちゃの種、ひまわりの種
- ダークチョコレート(カカオ70%以上)
◎ 食事のポイント
- カフェイン・アルコールの摂取は控えめに
- 甘いものの食べすぎは血糖値の乱れを招き、気分の不安定さに影響するので注意
● 適度な運動

運動はホルモンバランスや自律神経の調整に効果的です。
気分転換や睡眠の質向上にもつながるため、日々の習慣に取り入れるとPMS対策として有効です。
◎ おすすめの運動
- ウォーキング(1日30分ほど)
- ストレッチ・ヨガ(副交感神経を刺激し、リラックス)
- 軽い筋トレ(スクワット・腕立て)
- ダンスや水泳(音楽や水の刺激がリフレッシュ効果を高める)
◎ 運動のポイント
- 毎日少しずつ、無理のない範囲で続けることが大切
- 朝の光を浴びながら運動すると、ビタミンDの生成や体内時計の調整にも効果的
● ストレス管理
PMSはストレスによって悪化する傾向があります。
自律神経やホルモンバランスを整えるには、心のケアも欠かせません。
◎ 効果的なストレス対策
- ヨガ・ストレッチ(呼吸を意識して深く行う)
- 瞑想・マインドフルネス(「今」に集中することで心を落ち着かせる)
- アロマセラピー(ラベンダーやカモミールなどの香りが効果的)
- 趣味の時間をつくる(音楽・読書・料理・絵など)
◎ ポイント
- 深呼吸を意識的に取り入れる:「4-4-8呼吸法」(吸って4秒、止めて4秒、吐いて8秒)
- こまめな休憩でストレスを溜め込まない工夫も重要です。
● 質の良い睡眠
睡眠不足はホルモンバランスやストレス耐性の低下につながります。
質の良い睡眠を確保することで、PMSの症状を和らげやすくなります。
◎ 良質な睡眠のためのポイント
- 寝る前1時間はスマホ・PCを避ける(ブルーライトを減らす)
- 白湯やハーブティーなど温かい飲み物でリラックス
- 室温18〜22℃、湿度50〜60%に保つ
- ストレッチ・読書・アロマなどで「眠る前のルーティン」を作る
- 朝起きたら日光を浴びる(体内時計のリセット)
◎ 睡眠のポイント
- 睡眠は「時間より質」が重要
- 就寝3〜4時間前のカフェイン・アルコールは控える
PMSの治療は「体」と「心」の両方から
PMSは、薬だけに頼らず、日々の生活習慣の見直しとセルフケアによって改善が期待できる症状です。
症状がつらいときには、無理をせず医師や専門家のサポートを受けながら、自分に合った対処法を見つけていきましょう。
まとめ
PMSの症状は個人差が大きく、毎月の生活に影響を及ぼすこともあります。しかし、適切な治療と生活習慣の改善によって、症状を軽減し、より快適に過ごすことが可能です。

メンタルケア Lino clinic(リノクリニック)福岡天神院では、PMSに関する診療を行い、一人ひとりに合った治療方法を提案しています。当院は、赤坂駅・天神駅から徒歩圏内にあり、土日祝日も診療しているため、忙しい方でも通いやすい環境です。また、PMSの症状に対するカウンセリングも行っており、ホルモンバランスの調整やストレス管理について専門的なアドバイスを提供しています。
「生理前の不調を少しでも軽減したい」「自分に合った治療法を知りたい」とお考えの方は、ぜひLino clinicへご相談ください。